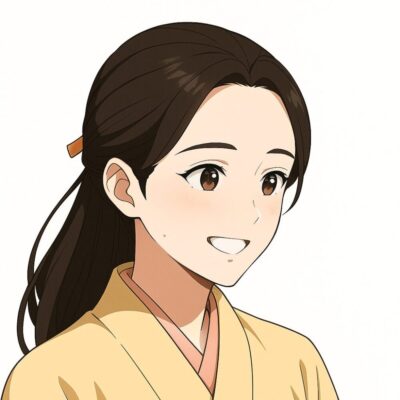戦国時代、天下統一を目指す武将たちの影には、彼らを支え、家を存続させる上で重要な役割を果たした女性たちがいました。徳川家康の側室、お万の方(おまんのかた)もまた、そうした女性の一人です。紀州徳川家や水戸徳川家という、後の徳川幕府を支えることになる御三家の祖となる子を産み、大奥という環境で波乱の時代を生き抜きました。一時期、尼となった経験もあるお万の方。その最期に詠んだとされる辞世の句には、彼女の世俗への思いと、来るべき死への静かな覚悟がにじみ出ています。
家康を支え、御三家を産む
お万の方は、永禄元年(1558年)頃、安房国の戦国大名・正木頼忠の娘として生まれました。後に徳川家康の側室となり、家康との間に二人の息子、すなわち後の紀州徳川家初代・頼宣(よりのぶ)と、水戸徳川家初代・頼房(よりふさ)を産みました。この二つの家は、後に尾張徳川家と合わせて「御三家」と呼ばれ、将軍家に後継ぎがない場合に将軍を出すことができる特別な家柄となり、徳川幕府の存続において極めて重要な役割を果たしました。お万の方は、直接政治に関わることはありませんでしたが、徳川家の血脈を繋ぎ、幕府の基盤を築く上で欠かせない貢献をしたと言えるでしょう。
お万の方の生涯には、一時期、世俗を離れて尼になった経験があったと伝えられています。これは、戦国の動乱や、大奥という独特の環境の中で、世の無常を感じたり、信仰に心を寄せたりしたためかもしれません。波乱の時代を生き抜き、息子たちが成長してそれぞれの家を興す姿を見届けたお万の方。彼女は穏やかで信仰深い人物であったと伝えられており、その最期は静かなものであったと考えられます。
「旅衣」に込めた覚悟
徳川家康の側室として、また御三家の母として波乱の時代を生き抜いたお万の方が、元和9年(1623年)に駿府(現在の静岡市)で亡くなる際に詠んだとされる辞世の句には、彼女の人生観と、死に対する静かな心境が表れています。
辞世の句:
「世の中を いとへどかねて 旅衣 つひにきるべき ときしもありけり」
これまでの人生で、私はこの世の中の煩わしさや無常さを感じて「世の中をいとい」てきた。しかし、いつかはこの世を離れる「旅」、すなわちあの世へ旅立つための「旅衣」を、ついに着なければならない時が来ることは、以前から分かっていたことなのだ。世俗への思いと、死への静かな覚悟が込められています。
句に込められた、達観の心
この辞世の句からは、お万の方が人生の終わりに達した、ある種の達観と、死への静かな受容の念が伝わってきます。
- 「世の中をいとへど」という実感: 徳川家康の側室として、権力の中心近くに身を置きながらも、世俗の煩わしさや、人間関係の複雑さ、あるいは人生の無常さを感じていたことがうかがえます。「いとへど」という言葉に、世に対するある種の厭離の感情が込められています。尼になった経験も、この世俗への思いと関連しているでしょう。
- 「かねて」からの死への意識: 「かねて」という言葉は、「以前から」「あらかじめ」という意味です。お万の方は、いつか死が訪れること、この世を去る日が来ることを、以前から意識していた、あるいは覚悟していたことを示しています。特に戦国という時代にあっては、人の命のはかなさを痛感することも多かったでしょう。
- 「旅衣つひにきるべきときしもありけり」という受容: 死を「旅立ち」と捉え、そのための「旅衣」を着る時が「ついに来た」と表現することで、自身の最期を穏やかに受け入れている様子がうかがえます。「~ときしもありけり」という詠嘆には、長い人生を経てたどり着いた、静かな感慨が込められています。
お万の方の辞世の句は、波乱の時代を生き抜き、家康を支え、子を育てた女性が、最期に世俗への思いと、死への静かな覚悟を示した、穏やかな言葉なのです。
お万の方の生涯と辞世の句
お万の方の生涯と辞世の句は、現代を生きる私たちにどのような示唆を与えてくれるでしょうか。
- 日常生活における「いとわしさ」との向き合い方: 彼女の「世の中をいとへど」という言葉は、現代社会でも多くの人が感じるであろう、日々の煩わしさやストレス、人間関係の悩みといった「いとわしさ」に共感させます。そうした感情を否定するのではなく、受け入れつつ、どのように心穏やかに生きていくか、という問いを投げかけています。
- 「旅衣」=死への心の準備: いつか誰もが「旅衣」を着る時が来ます。お万の方が「かねて」それを意識していたように、私たちも自身の終焉を意識することは、今をどう生きるか、何に価値を置くかを考える上で重要な視点を与えてくれます。穏やかな最期を迎えるために、どのような心の準備が必要かを考えるきっかけとなります。
- 人生における達観と心の平安: 波乱の時代を生き抜いたお万の方は、最期に死を静かに受け入れました。これは、人生の様々な経験を経てたどり着いた、ある種の達観した境地です。私たちも、人生における困難や無常さを受け入れ、そこに意味を見出すことで、心の平安を得られる可能性があることを示唆しています。
徳川家康の側室、お万の方の辞世の句は、激動の時代を生き抜いた一人の女性が、最期に世俗への思いと、死への静かな覚悟を示した魂の記録です。それは、現代に生きる私たちが、日々の煩わしさへの向き合い方、そして穏やかな最期を迎えるための心の準備について深く考えるきっかけを与えてくれる、時代を超えるメッセージなのです。
この記事を読んでいただきありがとうございました。