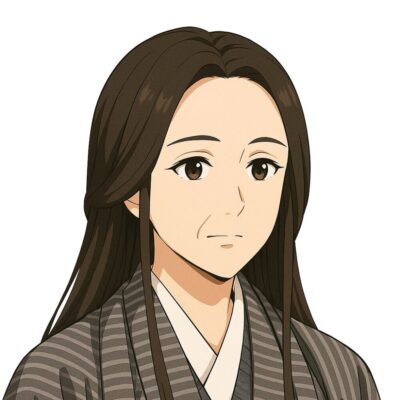江戸幕府三代将軍・徳川家光の乳母として、また大奥の創設者として、日本の歴史にその名を刻む女性、春日局(かすがのつぼね)。本名を福(ふく)と言い、逆境を乗り越え、将軍の乳母から幕政にまで影響力を持つほどの絶大な権力を手にしました。その生涯は、まさに波乱万丈そのものです。
権力の中枢で辣腕を振るった強い女性、というイメージが強い春日局ですが、その最期に遺したとされる辞世の句は、意外なほどに静かで敬虔な、仏教への深い帰依を感じさせるものです。
西に入る 月を誘い 法を得て 今日ぞ火宅(かたく)を のがれけるかな
逆賊の娘から大奥の支配者へ:春日局の生涯
春日局こと福は、明智光秀の重臣であった斎藤利三(さいとう としみつ)の娘として生まれました。しかし、父・利三が本能寺の変に関与したことで、福は「逆賊の娘」という重い十字架を背負うことになります。父は処刑され、福は母方の実家である稲葉家に身を寄せました。恵まれた出自とは言い難い、苦難の始まりでした。
その後、稲葉一族の稲葉正成(いなば まさなり)と結婚し、稲葉正勝(後の小田原藩主)を含む三人の子宝に恵まれますが、やがて離縁。福の人生が大きく転換するのは、二代将軍・徳川秀忠の嫡男・竹千代(後の家光)の乳母として江戸城に召し出されたことでした。どのような経緯で福が選ばれたのか、詳しい理由は定かではありませんが、この出来事が、福を歴史の表舞台へと押し上げます。
乳母となった福は、家光の養育に全身全霊を捧げます。特に有名なのが、将軍継嗣問題です。秀忠夫妻が家光よりも利発な弟・忠長を世継ぎにと考え始めた際、福は駿府の隠居・徳川家康に直訴するという大胆な行動に出て、家光の世継ぎとしての地位を確固たるものにしました。この一件は、福の忠誠心と行動力、そして政治的な駆け引きの才覚を示す象徴的なエピソードです。
家光が三代将軍に就任すると、福は朝廷から「春日局」の称号を賜り、その影響力は絶大なものとなります。大奥の制度を整備し、多くの女中たちを統率する最高権力者として君臨。将軍の私生活を取り仕切るだけでなく、幕政にも深く関与し、老中をも動かすほどの権勢を振るったと言われています。
辞世の句に込められた心境:「火宅」からの解放
将軍の乳母として、そして大奥の総帥として、激動の時代を生き抜き、強大な権力を手にした春日局。その人生の終わりに詠んだとされるのが、「西に入る 月を誘い 法を得て 今日ぞ火宅を のがれけるかな」という句です。
「西の空に沈みゆく月(=阿弥陀如来のいる西方浄土への導き)を心にしっかりと留め、仏様の教えに従って生きてきた今、ようやく私は、燃え盛る家のような、煩悩と苦しみに満ちたこの世(火宅)から解放されるのかな」。
この句からは、権力の頂点を極めた人物の最期とは思えないほど、穏やかで敬虔な心境が伝わってきます。「火宅」とは、仏教で迷いや苦しみに満ちた現世を例える言葉です。春日局は、自らの波乱に満ちた生涯を、まさに「火宅」のように感じていたのかもしれません。「逆賊の娘」という出自への苦悩、我が子と別れて乳母となった決断、将軍継嗣を巡る争い、大奥での権力維持のための心労…。華やかな権勢の裏にあったであろう、数々の苦しみや葛藤からの解放を、死を前にして静かに願っていたのではないでしょうか。
「西に入る月」に西方浄土への憧憬を見、「法を得て」と仏の教えへの帰依を示す言葉からは、春日局の篤い信仰心がうかがえます。人生の終わりに際し、権力や富といった世俗的な価値ではなく、仏法の導きによる魂の救済と安寧を求めた春日局の姿は、深く印象的です。権勢を極めた人物が最後に心の拠り所としたものが、静かな祈りであったことは、人生の意味を考えさせられます。
春日局の生き様と辞世の句は、現代社会を生きる私たちにも、多くのことを教えてくれます。
- 逆境を乗り越える意志の力: 不遇な出自にも屈せず、自らの力と才覚で道を切り開いた春日局の姿は、どんな困難な状況にあっても、強い意志と行動力があれば運命を変えられる可能性を示しています。諦めない心の大切さを教えてくれます。
- 目的達成への覚悟: 家光を将軍にするという目的のためには、手段を選ばず行動した春日局。その是非はともかく、目標達成に向けた強い覚悟と執念は、何かを成し遂げようとする際の原動力の重要性を教えてくれます。
- 心の平穏の追求: 社会的な成功や権力の頂点を極めても、人は心の安らぎや救いを求めるものです。春日局が最期に仏法に心の拠り所を見出したように、物質的な豊かさだけでなく、精神的な充足感や内面の平穏を大切にすることの重要性を示唆しています。
- リーダーシップと組織運営: 大奥という巨大な女性組織をまとめ上げ、厳格な規律をもって秩序をもたらした春日局の手腕は、現代の組織運営やリーダーシップ論においても、その功罪を含めて考察する価値があるかもしれません。
「逆賊の娘」から権力の頂点へ。激しい権力闘争の世を生き抜き、強大な影響力を持った春日局が、最期に願ったのは、仏の教えに導かれ、「火宅」のような現世から解き放たれることでした。その静かな祈りは、人生の栄華の儚さと、魂の救済という普遍的なテーマについて、深く考えさせられるものがあります。
この記事を読んでいただきありがとうございました。