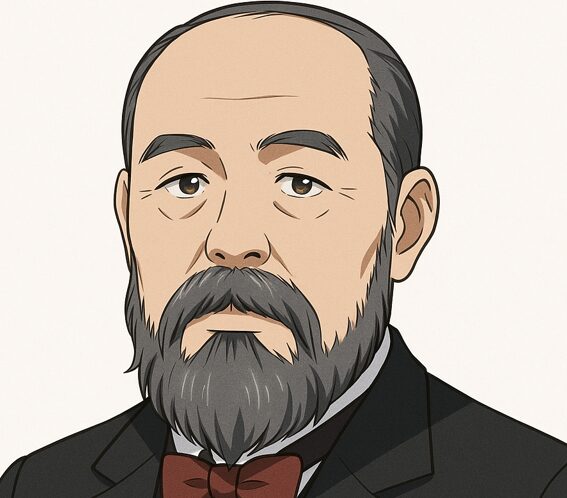「初代内閣総理大臣」—伊藤博文と聞いて、多くの日本人が思い浮かべるのは、この輝かしい称号でしょう。しかし、大日本帝国憲法の起草を主導し、近代日本の礎を築いたこの偉大な政治家が、幕末の動乱期にどのような青年時代を送っていたのかを知る人は多くありません。貧しい農家の生まれから、過激な攘夷活動に身を投じ、そして運命の英国留学を経て、現実主義的な政治家へと変貌を遂げる。この記事では、明治の元勲・伊藤博文の原点である、幕末の志士「伊藤俊輔(春輔)」としての活躍と苦悩、そして彼の生涯を貫く哲学が込められた名言の数々を深く掘り下げていきます。
伊藤博文とは:貧農から日本の初代宰相へ
伊藤博文の生涯は、まさに立身出世という言葉を体現したものでした。1841年、長州藩周防国(現在の山口県光市)の貧しい農家・林家の長男として生まれます。家計は苦しく、12歳で奉公に出されるなど、苦労の多い少年時代を過ごしました。彼の人生に転機が訪れたのは、父が長州藩の中間(武家奉公人)となり、それに伴い伊藤家を継いで足軽という低い身分ながらも武士階級に加わったことでした。
吉田松陰に見出された「周旋の才」
江戸湾警備の任に就いていた際、伊藤は人生の恩人となる来原良蔵と出会います。来原は吉田松陰の親友であり、桂小五郎の義弟でもある人物でした。彼の紹介で、伊藤は松下村塾の門を叩くことになります。松下村塾には、高杉晋作や久坂玄瑞といった、後に歴史を動かすことになる多くの俊英が集っていました。その中で、伊藤は剣術や学問の成績が突出していたわけではありません。しかし、師である吉田松陰は、伊藤の中に非凡な才能を見出していました。それが「周旋(しゅうせん)の才」です。「周旋」とは、人と人の間に立って物事を斡旋し、調整する能力のこと。現代でいう交渉力や調整能力、根回しの力です。松陰は、この実務家としての能力こそが、これからの時代に必要であると見抜いていたのです。
攘夷の志士から開国の現実主義者へ
松陰の死後、その遺志を継いだ伊藤は、当初、過激な尊王攘夷活動に身を投じます。しかし、ある経験が彼の思想を180度転換させることになりました。
過激な攘夷活動:英国公使館焼き討ち
師・松陰を処刑した幕府への憎しみと、異国を打ち払うべしという攘夷思想に燃えた若き日の伊藤は、高杉晋作らと共に過激な行動を繰り返します。幕府の要人暗殺計画に加わったり、1862年には品川御殿山に建設中だった英国公使館に火を放つなど、最も急進的な攘夷志士の一人として活動していました。この時の彼は、後に初代総理大臣として諸外国と渡り合う冷静な外交官の姿からは、想像もつかないほどの情熱と破壊衝動に満ちていました。
運命を変えた英国留学:長州五傑(ファイブ)として
そんな伊藤に、井上馨が秘密留学の話を持ちかけます。1863年、藩の禁を破り、井上馨、遠藤謹助、山尾庸三、野村弥吉と共に、後に「長州五傑(ちょうしゅうファイブ)」と呼ばれる5人の一人として、伊藤はイギリス・ロンドンへと旅立ちます。そこで彼が目にしたのは、想像を絶する光景でした。蒸気機関車が煙を上げて走り、巨大な軍艦が海を埋め尽くす。圧倒的な産業力と軍事力。日本の国力との差は、議論の余地もないほど明白でした。この時、伊藤は悟ります。「攘夷など、空理空論に過ぎない。このままでは日本は滅ぼされる。今は異国を打ち払うことではなく、彼らから学び、国力をつけることが先決だ」と。この経験が、彼の人生の決定的な転換点となりました。
高杉晋作の通訳として:下関戦争講和会議
留学からわずか半年後、長州藩が下関で外国船を砲撃したことへの報復として、英仏米蘭の四カ国連合艦隊が長州を攻撃するという報せが届きます(下関戦争)。国難を前に、伊藤と井上は急遽帰国。敗戦後、講和会議の大使となった高杉晋作の通訳として、伊藤は交渉の席に着きました。留学で培った英語力を駆使し、彼は高杉を補佐します。この交渉で、高杉は賠償金など多くの条件を受け入れましたが、ただ一点、「彦島の租借(領土の貸与)」だけは断固として拒否しました。後に伊藤は、「あの時、もし高杉さんが彦島を差し出していたら、日本は清国のように欧米の植民地となり、今の日本はなかっただろう」と回想しています。かつて焼き討ちにした英国の言葉を操り、国の主権を守る。この皮肉な状況こそ、彼が現実主義者へと生まれ変わった証でした。
幕末を駆け抜けた実務家として
帰国後の伊藤は、もはや過激な攘夷活動に身を投じることはありませんでした。その代わり、彼はその「周旋の才」を遺憾なく発揮し、倒幕への道を裏方として支え続けます。
高杉晋作の挙兵に一番駆け
下関戦争の敗北と、第一次長州征討により、長州藩内では幕府に恭順する保守派(俗論派)が実権を握ります。この藩の危機に、高杉晋作がわずか80名でクーデター(功山寺挙兵)を起こすと、伊藤は一番に駆けつけ、その革命を支えました。高杉という稀代の革命家を心から慕い、その行動を実務面でサポートする。ここに、彼の政治家としての役割の原型が見られます。
武器商人との交渉と薩長同盟
藩論が倒幕に統一されると、伊藤はその交渉能力と英語力を活かして、薩摩藩や英国商人グラバーとの武器購入交渉などで活躍します。また、歴史的な薩長同盟の締結においても、長州藩の代表の一人として交渉の場に参加するなど、着実にその存在感を高めていきました。表舞台で輝く高杉や桂の影で、伊藤は地道な交渉と根回しを続け、倒幕の実現に不可欠な役割を果たしたのです。
未来を見据える伊藤博文の名言集
彼の言葉は、その現実主義的な思想と、国家の未来を常に見据えていた広い視野を物語っています。
「大いに屈する人を恐れよ、いかに剛にみゆるとも、言動に余裕と味のない人は大事をなすにたらぬ。」
(本当に恐るべきは、大きく身をかがめて将来の飛躍に備えている人だ。どんなに強そうに見えても、言動に深みや余裕がない人は、大きな事を成し遂げることはできない。)
「今日の学問は全て皆、実学である。昔の学問は十中八九までは虚学である。」
(これからの時代に必要なのは、現実に役立つ実践的な学問だ。古い観念的な学問は、もはや通用しない。英国での経験から得た彼の確信が表れています。)
「いやしくも天下に一事一物を成し遂げようとすれば、命懸けのことは始終ある。依頼心を起こしてはならぬ。自力でやれ。」
(何かを成し遂げたいなら、常に命がけの覚悟が必要だ。人に頼ろうとするな、自分の力でやり遂げろ。貧しい身分から自力で道を切り拓いた彼の人生哲学です。)
「たとえここで学問をして業が成っても、自分の生国が亡びては何の為になるか。」
(国が滅びてしまっては、個人の学問や成功など何の意味もない。国家の存続こそが最優先であるという、彼の強い愛国心を示す言葉。)
「本当の愛国心とか勇気とかいうものは、肩をそびやかしたり、目を怒らしたりするようなものではない。」
(表面的な威勢の良さや排他的な言動が愛国心ではない。真の愛国心とは、もっと冷静で、国の将来を真剣に考える知的な営みであるという、彼の成熟した国家観がうかがえます。)
「お前に何でも俺の志を継げよと無理は言はぬ。持って生まれた天分ならば、たとえお前が乞食になったとて、俺は決して悲しまぬ。金持ちになったとて、喜びもせぬ。」
(我が子に対して、地位や財産ではなく、天賦の才を活かして自分らしく生きることを望んだ言葉。彼自身が身分によらず才能で認められた経験が反映されています。)
まとめ:近代日本の礎を築いたリアリスト
伊藤博文の幕末期は、思想の劇的な転換と、実務家としての才能の開花に集約されます。攘夷という観念的な思想から、開国と近代化という現実的な路線へ。その転換点にあったのは、自らの目で世界の現実を見た英国留学の経験でした。彼は、理想を語るだけでなく、それを実現するための地道な交渉や調整を厭わない現実主義者(リアリスト)でした。この「周旋の才」こそが、維新後の対立と混乱に満ちた新政府をまとめ上げ、初代総理大臣として近代日本の設計図を描く上で、最大の武器となったのです。幕末の動乱の中で培われた彼の現実感覚と国際感覚なくして、今日の日本の礎はなかったと言っても過言ではないでしょう。
この記事を読んでいただきありがとうございます。