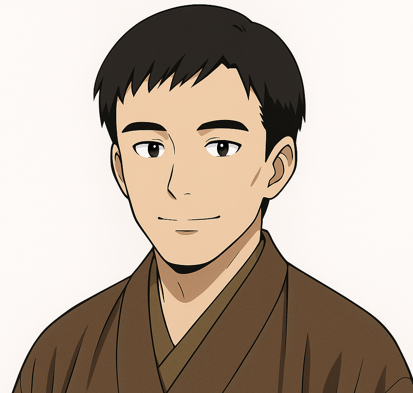「おもしろき こともなき世を おもしろく」という辞世の句で知られる高杉晋作。彼は、幕末という激動の時代を、誰よりも熱く、そして誰よりも自由に駆け抜けた革命児です。吉田松陰の教えを受け、奇兵隊を創設し、長州藩を倒幕へと導いた彼の生涯は、わずか29年という短さでした。この記事では、高杉晋作の破天荒ながらも国を想う情熱に満ちた生涯、後世に語り継がれる功績、そして現代人の心にも響く名言の数々を詳しく解説します。
高杉晋作とは:時代が求めた型破りな天才
高杉晋作は、江戸時代末期の長州藩士であり、幕末の動乱期に最も輝いた志士の一人です。彼の行動は常に型破りで、藩から支給された洋行費で遊興にふけったかと思えば、その知識を活かして独断で軍艦を購入するなど、周囲を驚かせる逸話には事欠きません。地位や名誉に無欲で、酒と女性を愛する自由奔放な人物でしたが、その根底には常に国を憂う強い気持ちと、時代を動かすための明確なビジョンがありました。身分にとらわれない奇兵隊の結成や、絶望的な状況を覆したクーデターの成功など、彼の行動力とカリスマ性は、日本の歴史を大きく転換させる原動力となったのです。
師・吉田松陰からの評価
晋作の才能を早くから見抜いていたのが、師である吉田松陰です。松陰は「学問は未熟でわがままなところもあるが、有識の士である。十年後にはすぐれた仕事をなすだろう」と評しました。その言葉通り、晋作の学識と洞察力は急速に成長し、やがて松陰に「なにかを決定するときは、晋作の意見に従う」と言わしめるほどの信頼を得るに至ります。
盟友・伊藤博文から見た晋作
初代総理大臣となった伊藤博文は、兄貴分であった晋作をこう評しています。
動けば雷電の如く 発すれば風雨の如し、
(動けば雷のようで、言葉を発すれば嵐のようである)
衆目駭然、敢て正視する者なし。
(多くの人はただただ驚き、あえて正視する者すらいない)
これ我が東行高杉君に非ずや
(これこそ、我らの高杉晋作さんなのである)
この言葉は、晋作の圧倒的な行動力と存在感を的確に表現しています。
激動の生涯:倒幕への軌跡
生い立ちと松下村塾での学び
1839年、長州藩の城下町・萩で生まれた晋作は、幼い頃から剣術に励み、柳生新陰流の免許皆伝を得るほどの腕前でした。藩校・明倫館を経て吉田松陰の松下村塾に入門すると、久坂玄瑞や伊藤博文といった生涯の同志と出会い、松陰の教えを受けて倒幕思想に目覚めていきます。
江戸遊学と過激な攘夷活動
江戸へ遊学した晋作は、積極的に学問に取り組む一方、尊王攘夷派の志士として活動を始めます。生麦事件をきっかけに外国人襲撃を計画したり、品川に建設中の英国公使館を焼き討ちにするなど、過激な行動でその名を知られるようになりました。
奇兵隊の結成と長州藩の孤立
外国船との戦いを経て、旧来の武士だけの軍隊では通用しないと痛感した晋作は、1863年に身分を問わず志ある者を集めた「奇兵隊」を結成します。これは、武士の時代を終わらせ、近代的な国民皆兵制度へと繋がる画期的な試みでした。
しかし、京都で勢力を伸ばしていた長州藩は、会津藩・薩摩藩らの策略により失脚(八月十八日の政変)。勢力挽回を狙って京都に出兵するも大敗を喫し(禁門の変)、朝敵となってしまいます。
四国連合艦隊との講和交渉:日本の危機を救う
朝敵となった長州藩に追い打ちをかけるように、以前の外国船砲撃の報復として、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国連合艦隊が下関を攻撃。藩が存亡の危機に瀕する中、講和交渉の大使に抜擢されたのが晋作でした。
彼は、賠償金など多くの要求を受け入れつつも、領土の割譲にあたる「彦島の租借」だけは断固として拒否。アヘン戦争後の清の惨状を知っていた晋作は、領土を渡すことが植民地化への第一歩だと見抜いていたのです。さらに「攘夷は幕府の命令に従ったまで」と主張し、賠償金の支払い責任を幕府に押し付けるという離れ業を成し遂げ、日本の主権を守りました。
功山寺挙兵:わずか84名でのクーデター
禁門の変と四国艦隊との敗戦後、幕府による第一次長州征討を前に、長州藩内では幕府に恭順する保守派(俗論派)が実権を握ります。改革派の志士たちは処刑され、晋作も命を狙われる身となりました。
藩の未来に絶望した晋作は、1865年、下関の功山寺で決起します。当初彼に従ったのは伊藤博文が率いる力士隊などわずか84名。対する藩の正規軍は数千人。誰もが無謀だと考えた戦いでしたが、晋作の卓越した戦略とカリスマ性に惹かれ、奇兵隊をはじめ井上馨、山県有朋らかつての仲間が次々と合流。奇跡的な勝利を重ね、クーデターを成功させます。これにより藩論は再び「倒幕」に統一され、晋作は長州藩の実権を握りました。
薩長同盟と最期の戦い
藩の実権を握った晋作は、坂本龍馬や中岡慎太郎の仲介のもと、宿敵であった薩摩藩と軍事同盟(薩長同盟)を締結。これにより、倒幕への流れは決定的となります。
幕府による第二次長州征討では、海軍総督として自ら軍艦に乗り込み、幕府艦隊を奇襲して打ち破るなど目覚ましい活躍を見せました。しかし、長年の持病であった肺結核が悪化。大政奉還という歴史の転換点を見ることなく、1867年に29歳の若さでその生涯を閉じました。
心を揺さぶる高杉晋作の名言集
おもしろき こともなき世を おもしろく。
戦いは一日早ければ一日の利益がある。まず飛びだすことだ。思案はそれからでいい。
人間、窮地におちいるのはよい。意外な方角に活路が見出せるからだ。
しかし、死地におちいれば、それでおしまいだ。だから、おれは困ったの一言は吐かない。
苦しいという言葉だけは、どんなことがあっても、言わないでよそうじゃないか。
負けて退く人をよわしと思うなよ。知恵の力の強きゆえなり。
人間は、艱難は共にできる。しかし富貴は共にできない。
人は旧を忘れざるが義の初め。
三千世界の烏を殺し、主と朝寝がしてみたい。
友の信を見るには、死、急、難の三事をもって知れ候。
苦労する身は厭わねど、苦労し甲斐のあるように。
翼あらば 千里の外も飛めぐり よろづの国を 見んとぞおもふ。
死んだなら 釈迦や孔子に 追いつきて 道の奥義を 尋ねんとこそ思へ。
後れても 後れてもまた 後れても 誓ひしことを 豈忘れめや
人間味あふれる高杉晋作の漢詩
詩を愛し、三味線を嗜んだ晋作は、人間味あふれる漢詩も残しています。
妻児将到我閑居(妻児まさにわが閑居に到らんとす)
妾婦胸間患余有(妾婦胸間患い余りあり)
従是両花争開落(これより両花開落を争う)
主人拱手莫如何(主人手をこまねいて如何ともするなし)
数日来鶯鳴檐前不去(数日来鶯檐前に鳴いて去らず)
賦之与(これを賦して与える)
一朝檐角破残夢(一朝檐角(たんかく)残夢を破る)
二朝窓前亦弄吟(二朝窓前(そうぜん)に亦弄吟(ろうぎん)す)
三朝四朝又朝々(三朝四朝又朝々)
日々懇来慰病痛(日々懇来し病通を慰む)
君於方非有旧親(君は方(まさ)に於いて旧親あるに非ず)
又非寸恩在我身(又寸恩我が身に存すに非ず)
君何於我誤看識(君何ぞ我に於いて看識を誤る)
吾素人間不容人(吾素より人間に容れられず)
故人責吾以詭智(故人吾を責むるに詭智(きち)を以てす)
同族目我以放恣(同族我を目するに放恣(ほうし)を以てす)
同族故人尚不入(同族故人尚入れず)
而君我容遂何意(而して君吾を容るる遂に何の意ぞ)
君勿去老梅之枝(君去る勿(なか)れ老梅の枝)
君可憩荒溪之湄(君憩うべし荒溪の湄(みぎわ))
寒香淡月我欲所(寒香淡月は我が欲する所)
為君執鞭了生涯(君が為に鞭を執って生涯を了らん)
まとめ
高杉晋作は、既存の価値観や常識に縛られることなく、自らの信念と情熱に従って行動し続けた人物でした。その行動は時に「破天荒」と評されますが、すべては日本という国を憂い、未来を切り拓くためのものでした。彼の創設した奇兵隊は新しい時代の軍隊のモデルとなり、彼の命がけの交渉やクーデターがなければ、明治維新の実現はもっと遅れていたか、あるいは全く違う形になっていたかもしれません。わずか29年で幕末の世を駆け抜けた高杉晋作の生き様と、彼の遺した言葉は、変化を恐れずに行動することの大切さを、現代を生きる私たちに教えてくれています。
この記事を読んでいただきありがとうございました。