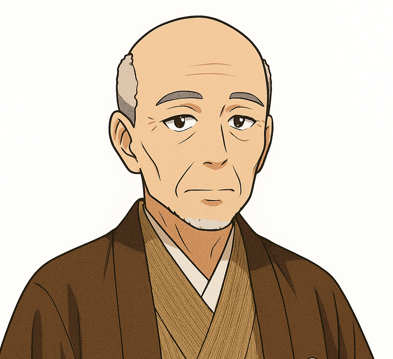「沖田は猛者の剣、斎藤は無敵の剣」—。新選組最強の隊士として知られた永倉新八は、かつての仲間たちをそう評したといいます。幕末最強の剣客集団・新選組において、一番隊組長・沖田総司と並び、常に最強の一人としてその名が挙がるのが、三番隊組長・斎藤一です。しかし、彼の特異性はその剣の腕前だけではありません。
近藤、土方、沖田をはじめ、多くの隊士が志半ばで命を落とす中、斎藤は新選組の義を貫きながらも、戊辰戦争、そして明治という新しい時代を生き抜き、大正の世までその生涯を全うしました。この記事では、謎に包まれた出自、新選組の「牙」として暗躍した京都時代、そして明治を生き抜いた「藤田五郎」としての後半生まで、沈黙の剣客・斎藤一の生涯の軌跡を深く掘り下げていきます。
斎藤一とは:謎に包まれた「無敵の剣」
映画『壬生義士伝』では物語の語り部として、漫画『るろうに剣心』では明治の警官として、数々の創作物で重要な役割を担う斎藤一。その人物像は、常に冷静沈着で、感情を表に出さず、ただ己の信念と任務にのみ生きる孤高の剣客として描かれます。これは、彼の言葉数が少なく、その出自や経歴に不明な点が多いことに起因します。彼は自らを語らず、ただその「剣」によって己の存在を証明し続けました。その姿は、光の当たる場所で組織を率いた近藤勇や、華やかな伝説に彩られた沖田総司とは対照的に、新選組という組織の「影」そのものでした。
謎多き出自と剣の流派
1844年1月1日生まれであることから「一(はじめ)」と名付けられたとされる彼の前半生は、厚いベールに包まれています。御家人の子として江戸で生まれたとも、播磨国明石の出身であるとも言われていますが、確たる証拠はありません。確かなのは、19歳で京都に現れる前、江戸で口論の末に旗本を斬殺し、追われる身となって京へ逃れた、という逸話です。京都では父の知人を頼り、剣術道場で師範代を務めていたところ、幕府が募った「浪士組」の人員募集を知り、これに参加。ここから、彼の剣客としての公式な歴史が始まります。
その剣の流派もまた謎の一つです。一説には必殺の居合術を得意としたことから「無外流」や「一刀流」とも言われますが、彼自身が流派を語った記録はありません。また、必殺の間合いが独特であったことから「左利き」であったという説も根強く、そのミステリアスな剣技は、彼の人物像をより一層魅力的なものにしています。
新選組の「牙」:粛清と諜報の暗躍
京で結成された壬生浪士組(後の新選組)に加わった斎藤は、入隊後すぐにその実力を認められ、幹部である「副長助勤」に抜擢されます。出自も年齢も関係ない、実力のみが評価される新選組において、彼の剣がいかに突出していたかがうかがえます。後に組織が整えられると、三番隊組長兼撃剣師範に就任。彼は、近藤・土方が目指す「武士集団」を創り上げるために、その最も鋭い「牙」として、内部の敵に向けられました。
内部粛清の実行者
新選組の名を天下に轟かせた「池田屋事件」では、土方歳三の隊に所属。直接の斬り込みには参加していませんが、その後の恩賞の記録から、逃亡する浪士を斬るなど、何らかの武功を立てたと考えられています。この事件以降、斎藤の剣は主に組織内部に向けられます。局長・近藤勇や副長・土方歳三の密命を受け、隊の規律を乱す者や、組織に害をなす者を次々と粛清していきました。五番隊組長・武田観柳斎や七番隊組長・谷三十郎など、粛清された幹部隊士の多くは、斎藤の刃にかかったと伝えられています。彼は、組織の結束を守るため、冷徹に汚れ役を引き受け続けたのです。
間者としての暗躍:御陵衛士潜入
斎藤の暗躍が最も際立ったのが、参謀であった伊東甲子太郎との対立です。思想の違いから、伊東は新選組を離脱し、独自の組織「御陵衛士」を結成します。この時、斎藤は伊東派に加わるふりをして御陵衛士に潜入。内部の情報を逐一、近藤・土方に報告する「間者(スパイ)」としての役割を担いました。斎藤がもたらした情報に基づき、新選組は伊東甲子太郎を暗殺。さらに、その遺体を引き取りに来た御陵衛士の残党を待ち伏せして殲滅します(油小路事件)。この諜報活動における彼の功績は、新選組の分裂という最大の危機を救ったと言っても過言ではありません。
戊辰戦争と「会津の士」への転身
大政奉還、そして戊辰戦争の勃発により、新選組は「賊軍」として新政府軍との泥沼の戦いに身を投じていきます。この絶望的な戦いの中で、斎藤の忠義の対象は、新選組という組織から、彼らが守護し続けた「会津藩」そのものへと昇華されていきました。
局長・近藤勇の死を超えて
鳥羽・伏見の戦いに敗れ、江戸へ敗走。甲州勝沼の戦いにも敗れ、局長・近藤勇が捕らえられ斬首されると、新選組は事実上の瓦解状態となります。しかし、斎藤は戦うことをやめませんでした。彼は残った隊士を率いて、戦いの舞台が移った会津へと向かいます。彼にとって、戦いはまだ終わっていなかったのです。もはや彼の忠誠は、近藤個人に対するものではなく、新選組が命を懸けて守ろうとした会津藩主・松平容保へと捧げられていました。
会津での死闘と降伏
会津戦争において、斎藤は会津藩の指揮下に入り、「山口二郎」と名を変えて奮戦します。特に、若松城下が戦火に包まれる中、如来堂で僅かな兵と共に新政府軍を迎え撃った戦いは壮絶を極めました。彼はここで、文字通り死ぬまで戦う覚悟でした。しかし、これ以上の抵抗は無意味と判断した会津藩からの説得を受け、ついに投降。捕虜となりますが、その命は長らえました。
明治を生きる:元・新選組最強の剣客、藤田五郎
戦争を生き延びた斎藤は、かつての仲間たちが夢見た「武士」としての生き方を、新しい時代の中で模索し始めます。
斗南藩士・藤田五郎として
降伏後、会津藩は下北半島の不毛の地で「斗南藩」として再興を許されます。斎藤もまた、斗南藩士として移住。そこで、会津藩の名家老の娘であった高木時尾と再婚します。この時、斎藤は「藤田五郎」と改名。驚くべきことに、この結婚の仲人を務めたのは、元会津藩主・松平容保その人でした。これは、斎藤が会津藩からいかに深く感謝され、信頼されていたかを示す、何よりの証拠と言えるでしょう。
警視庁抜刀隊としての西南戦争
1874年、東京へ移住した藤田五郎(斎藤一)は、その剣腕を買われ、警視庁に採用されます。そして1877年、西郷隆盛が士族を率いて蜂起した「西南戦争」が勃発。彼は警部補として、刀で斬り込む「抜刀隊」の一員として従軍します。かつて京で敵対した薩摩藩の兵士たちを相手に、彼は獅子奮迅の働きを見せ、その武功は新聞にも掲載されたほどでした。それは、新政府の警察官としての任務であると同時に、京で散っていった新選組の仲間たちの仇を討つ、私的な復讐戦であったのかもしれません。
座したままの往生:武士としての最期
警視庁を退職した後は、東京高等師範学校などで庶務係として静かな晩年を送りました。そして1915年9月28日、胃潰瘍のため死去。享年72。伝えられるところによれば、彼は死の直前、床の間で正座し、静かに息を引き取ったといいます。それは、激動の時代を生き抜き、天寿を全うした男の、あまりにも見事な、武士としての最期でした。
まとめ:誠の旗を胸に、時代を生き抜いた男
斎藤一の生涯は、新選組の「誠」の旗の下に始まり、会津藩への忠義へと続き、そして明治国家への奉職へと至りました。彼は、時代の変化に適応しながらも、その中心にある武士としての魂を決して失いませんでした。彼は多くを語りませんでしたが、その生き様そのものが、死んでいった仲間たちの分まで生きるという、強い意志の表れだったのではないでしょうか。
沖田が時代に咲いた「徒花」ならば、斎藤は時代の「礎石」となった男。その沈黙の剣客の生涯は、本当の強さとは何か、そして忠義とは何かを、私たちに静かに問いかけ続けています。
この記事を読んでいただきありがとうございました。