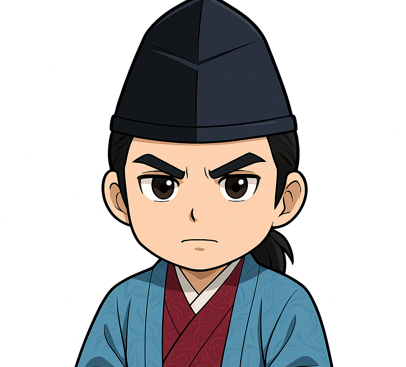日本の歴史上、最も有名な謀反の一つ「本能寺の変」。その中心人物として、明智光秀(あけち みつひで)の名を知らない人はいないでしょう。「裏切り者」「逆臣」というレッテルを貼られる一方で、優れた知性と教養を持つ武将であったとも言われています。彼の行動の真意は今なお謎に包まれていますが、最期に残したとされる辞世の句には、その複雑な胸中が垣間見えます。今回は、光秀の言葉を手がかりに、彼の人物像と、現代を生きる私たちが「働く意味」を考える上でのヒントを探ってみましょう。
本能寺、そして山崎へ – 栄光と没落
織田信長の信頼を得て、重臣にまで上り詰めた明智光秀。彼は、優れた行政手腕や文化的な素養を持ち、信長の天下統一事業に貢献しました。しかし、天正10年(1582年)6月2日、突如として主君・信長に刃を向けます。本能寺で信長を討ち取った後、光秀は一時的に天下人の地位に近づきますが、中国地方から驚異的な速さで引き返してきた羽柴(豊臣)秀吉に山崎の戦いで敗れ、その「三日天下」は終わりを告げました。敗走中に落命したとも、自害したとも言われています。
なぜ光秀は信長を裏切ったのか? 野望、怨恨、あるいは守るべきものがあったのか… その動機については諸説あり、歴史の大きな謎とされています。確かなことは、彼がその行動によって、自らの運命も、日本の歴史も大きく変えたということです。
二つの辞世の句を読む – 光秀の心の内
光秀が最期に残したとされる辞世の句は、二種類伝わっています。それぞれに、彼の異なる心境が表れているようで興味深いものです。
【悟りの境地】
順逆二門(じゅんぎゃくにもん)に無し
大道(だいどう)心源(しんげん)に徹(てっ)す
五十五年(ごじゅうごねん)の夢(ゆめ)
覚(さ)め来(きた)れば 一元(いちげん)に帰(き)す
(意訳:正しいとか間違っているとか、従うとか逆らうとか、そういう相対的な二つの門などは本来存在しない。宇宙の真理(大道)は、心の奥底(心源)にまで通じているのだ。この世で過ごした五十五年の人生も夢のようなもの。今、夢から覚めてみれば、すべては元の一つ(一元)に帰していくだけだ。)
この句からは、仏教的な無常観や、物事を相対的な価値観(順/逆、善/悪)を超えた次元で捉えようとする、ある種の悟りの境地が感じられます。自らの行動を、世俗的な批判を超えた、より大きな宇宙の法則や真理の中に位置づけようとしたのでしょうか。人生を「夢」と捉え、死を「本来の根源に帰ること」と静かに受け入れているようにも読めます。
【不屈の意志】
心しらぬ 人は何とも 言はばいへ
身をも惜(お)しまじ 名をも惜しまじ
(意訳:私の本当の心を知らない人たちが、何とでも言うがよい。この命が惜しいとも思わないし、(どのような汚名を着せられようと)名誉や評判が惜しいとも思わない。)
こちらは一転して、強い意志と、世評に対するある種の開き直りとも言える感情が表れています。「心しらぬ人」という言葉に、自らの真意が理解されないことへの無念さや孤独感が滲む一方で、「言はばいへ」という部分には、他者の評価に惑わされず、自らの信念を貫いたという自負心が見え隠れします。「身をも惜しまじ、名をも惜しまじ」という潔い言葉は、全ての責任を一身に負い、結果を受け入れる覚悟を示しています。
あなたの「働く理由」は?
明智光秀の辞世の句は、時代を超えて、私たち自身の生き方や働き方について考えるきっかけを与えてくれます。特に、現代社会で多くの人が抱える「働く理由」についての悩みと響き合う部分があるのではないでしょうか。
- 理解されない苦しみと向き合う: 「心しらぬ人」に何を言われようとも、という光秀の態度は、現代の職場でも起こりうる「正当に評価されない」「自分の意図が伝わらない」といった状況と重なります。彼の言葉は、他者の評価に一喜一憂せず、自分の仕事への取り組みや信念に軸足を置くことの大切さを教えてくれるかもしれません。
- 「働く理由」の根源を探る: 光秀が「順逆」という二元論を超えた「大道」「心源」に思いを馳せたように、私たちも日々の仕事の意味を、給料や地位といった目に見えるものだけでなく、もっと深いレベルで問い直すことが大切です。「何のために働くのか?」その答えは、壮大なビジョンである必要はありません。生活のため、家族のため、自己成長のため、社会貢献のため… 自分自身の「心源」にある働く理由を見つめ直す時間を持つことが、迷いや不安を乗り越える力になるでしょう。
- 仕事との向き合い方を選ぶ: 光秀が自らの人生を「夢」と捉え、その結末を受け入れたように、現状の仕事が希望通りでなくても、その状況を一旦受け入れた上で、「どう向き合うか」は自分で選べます。「生活のため」という理由も立派な動機です。その上で、「仕事の中に楽しみを見出す」「やりがいを感じる瞬間を探す」など、仕事への関わり方を変えていくことは可能です。報酬のためだけでなく、自分が「面白い」「やってみたい」と感じることに挑戦してみることで、仕事への新たな意味が見つかるかもしれません。
- 揺るがない自分を持つ: 「身をも惜しまじ、名をも惜しまじ」という言葉は、極端ではありますが、周囲に流されず、最終的に自分の行動や人生に責任を持つという覚悟を示しています。働く上で、困難や理不尽に直面したとき、最後に頼りになるのは自分自身の価値観や信念なのかもしれません。
明智光秀という人物は、その評価が大きく分かれる、まさに光と影を持つ存在です。しかし、彼の残した言葉は、人生の岐路や困難に直面した人間の、普遍的な苦悩や覚悟を映し出しています。彼の辞世の句に耳を傾けることで、私たちは自らの「働く理由」を問い直し、日々の仕事に新たな意味を見出すヒントを得られるのではないでしょうか。
この記事を読んでいただきありがとうございました。