 戦国武将の名言
戦国武将の名言 「渋柿を切って甘柿を継ぐのは小心者のすることだ」—武田信玄の名言が教える人の使い方
「渋柿を切って甘柿を継ぐのは小心者のすることだ」—信玄が教える人の使い方の極意武田信玄は、部下の使い方において「渋柿を切って甘柿を継ぐのは小心者のすることだ」と語りました。この言葉は、どんな人でもその特性に合った使い方をすれば、良い結果を生...
 戦国武将の名言
戦国武将の名言  戦国武将の名言
戦国武将の名言  戦国武将 辞世の句
戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句
戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句
戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句
戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句
戦国武将 辞世の句 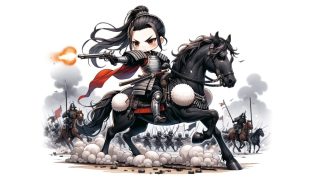 戦国武将の名言
戦国武将の名言 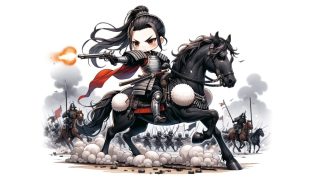 戦国武将の名言
戦国武将の名言 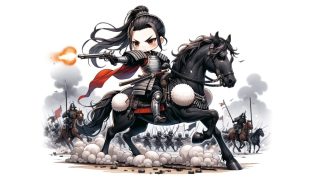 戦国武将の名言
戦国武将の名言