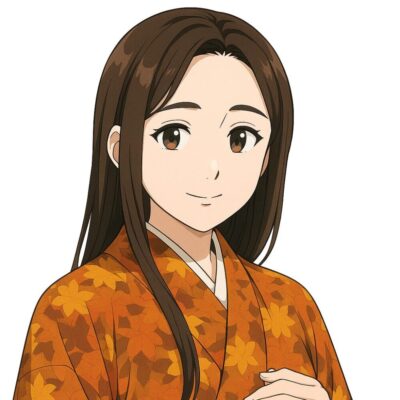ビジネスシーンにおいて、こちらの不手際やミスにより、上司や、特に大切な取引先に謝罪をしなければならない場面は、残念ながら誰にでも起こり得ます。その際、私たちは謝罪の意を示すため、「この度は、誠に申し訳ございません」「深くお詫び申し上げます」といった、正しい敬語を使います。
しかし、相手がすでに怒りや不信感を抱いている状況で、これらの「正しいだけの謝罪」を伝えても、「形式的だ」「本当に悪いと思っているのか」と、かえって相手の感情を逆なでしてしまう危険性があります。相手の怒りを鎮め、信頼を回復するためには、謝罪の言葉そのものよりも、その謝罪の言葉を受け入れてもらうための「地ならし」が不可欠です。
本記事では、「お詫び申し上げます」という謝罪の言葉の「直前」に添えるだけで、相手の怒りや失望の感情に寄り添い、あなたの謝罪を「心のこもったもの」として受け止めてもらうための、「魔法の一言」とも言えるクッションフレーズのテクニックを、具体的なメール術とともに解説します。
「お詫び申し上げます」だけでは「心」が伝わらない構造分析
まず、なぜ「お詫び申し上げます」という完璧な敬語だけでは、相手の怒りが鎮まらないのか。その構造を分析します。
謝罪の言葉は「こちらの都合」
「お詫び申し上げます」という言葉は、「私(話し手)」が「お詫びを申し上げる」という行為をへりくだって行う、謙譲語です。これはあくまで、「自分が謝罪した」という事実を表明しているにすぎません。
しかし、不利益を被り、怒っている相手(聞き手)が聞きたいのは、こちらの謝罪表明ではありません。相手が最も知りたいのは、「あなたは、私がどれほど迷惑し、どれほど不快に感じているかを、ちゃんと理解しているのか?」という、自分(相手)の感情への共感です。
「魔法の一言」の役割:相手の感情への「共感」
相手の怒りを鎮めるために必要なのは、謝罪の言葉の前に、まず「あなたが被った不利益や不快な感情を、私は確かに認識しています」という「共感」のメッセージを明確に示すことです。
この「共感の一言」こそが、相手の心のガードを解き、こちらの謝罪の言葉を受け入れてもらうための「魔法の一言」として機能します。
NG例(謝罪が先):
「この度は、誠に申し訳ございませんでした。弊社のミスにより、〇〇様にご迷惑をおかけしました。」
(謝罪が先に来ており、相手の迷惑を「他人事」のように説明している印象を与えます。)
OK例(共感が先):
「この度は、弊社のミスにより、〇〇様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
(先に「迷惑をかけた」という相手の被害事実を認め、それに対して謝罪する、という正しい順序になっています。)
【パターン別】「お詫び」の前に添える「魔法の一言」フレーズ集
相手が感じているであろう「不快感」や「負担」の種類に応じて、この「共感の一言」を使い分けることが、プロフェッショナルな謝罪術です。
パターン1:相手を「不快」にさせた時(感情への共感)
こちらの対応の悪さや、失礼な言動などで、相手の感情を害してしまった場合に使うフレーズです。
- 「〇〇様にご不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。」
- 「〇〇様のお気持ちを害する結果となりましたこと、誠に申し訳ございません。」
パターン2:相手に「手間」をかけさせた時(負担への共感)
こちらのミスにより、相手に余計な作業や、再確認などの「手間」を発生させてしまった場合に使います。
- 「〇〇様に多大なるお手間を取らせてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。」
- 「〇〇様に何度もご確認いただく事態となりましたこと、誠に申し訳ございませんでした。」
パターン3:相手を「不安」にさせた時(状況への共感)
納期遅延の懸念や、連絡の不備などで、相手を「どうなっているのだろう」と不安な状態にさせた場合に使います。
- 「〇〇様に多大なるご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
- 「〇〇様をご不安なお気持ちにさせてしまいましたこと、弁解の言葉もございません。」
パターン4:相手の「期待」を裏切った時(失望への共感)
相手の信頼や期待に応えられず、失望させてしまったことが明らかな場合に使います。
- 「〇〇様のご期待に沿うことができず、誠に申し訳ございません。」
- 「〇〇様のご信頼を損ねる結果となりましたこと、深く反省しております。」
謝罪メールでの実践的な使い方と例文
これらの「魔法の一言」を、謝罪メールの冒頭に組み込むことで、その後の謝罪が相手に届きやすくなります。
謝罪メールの基本構成
- 魔法の一言(相手の被害への共感) + 謝罪の言葉
- 原因の説明(言い訳にならないよう、事実を簡潔に)
- 今後の具体的な対策(どうリカバリーするか)
- 改めての謝罪と結びの言葉
例文1:納品ミス(相手に手間をかけさせた)
件名:納品物の不備に関するお詫び
株式会社〇〇 〇〇様
いつもお世話になっております。株式会社△△の佐藤です。
この度は、昨日納品いたしました〇〇について、内容に重大な誤りがございました。
〇〇様にお手間を取らせてしまいましたこと、ならびに多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
(中略:原因と対策)
取り急ぎ、お詫びとご報告を申し上げます。
引き続き、誠心誠意対応してまいりますので、何卒ご容赦いただけますようお願い申し上げます。
例文2:担当者の対応不備(相手を不快にさせた)
件名:弊社担当者の対応についてのお詫び
株式会社〇〇 〇〇様
いつも大変お世話になっております。株式会社△△の鈴木です。
この度、弊社担当者〇〇の未熟な対応により、〇〇様に大変ご不快な思いをさせてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
(中略:原因と対策、担当者変更の提案など)
〇〇様のご信頼を回復できますよう、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。
この度の件、重ねて深くお詫び申し上げます。
注意点:「魔法の一言」は「言い訳」ではない
このテクニックを使う上で、絶対に間違えてはならないのは、「相手の感情に寄り添う」ことと、「言い訳をする」ことを混同しないことです。
NG例:「当方の確認が不足しておりましたが、お詫び申し上げます。」
(これは、謝罪の前に「原因(言い訳)」が先に来ています。相手は「あなたの確認不足など知ったことではない」と感じます。)
OK例:「当方の確認不足により、〇〇様にご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。」
(これは、原因によって相手が被った「被害」に焦点を当て、そこに共感しています。)
謝罪の第一声は、必ず「相手が主語」の言葉(あなたが被った被害)でなければなりません。
まとめ:謝罪は「共感」から始まる
相手の怒りを鎮めるのは、「お詫び申し上げます」という謝罪の言葉そのものではありません。その言葉の前に添えられた、「あなたの不快感・ご負担を、私は確かに理解しています」という、真摯な「共感」のメッセージです。
ミスが起きてしまった時こそ、形式的な謝罪に逃げず、まずは相手の感情に寄り添う「魔法の一言」を添えること。それこそが、壊れかけた信頼関係を修復し、より強固なパートナーシップへと繋げる、プロフェッショナルな謝罪術と言えるでしょう。
この記事を読んでいただきありがとうございました。