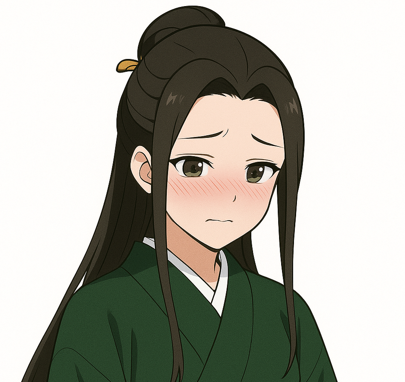敬語の落とし穴を避けるために
ビジネスシーンにおいて、上司や取引先、お客様の「帰る」という動作を丁寧に伝える際、「お帰りになられました」という表現を使ってしまうことはないでしょうか。相手への最大限の敬意を込めて発したこの一言が、実は日本語の敬語のルールから見ると「二重敬語」という誤った表現にあたる可能性があります。敬意を尽くそうとするあまり、かえって不自然な表現になってしまうことは、敬語を使う上で避けて通れない落とし穴の一つです。
「帰る」という動作に関する敬語は、相手の動作を高める「尊敬語」と、自分の動作をへりくだる「謙譲語」の使い分けはもちろん、一つの表現の中に敬語要素を重ねてしまわないかという、細やかな配慮が求められます。この正しい敬語のルールを理解し、洗練された表現を使いこなすことが、相手に安心感と好印象を与えるための鍵となります。
本記事では、「帰る」という動作の敬語表現に焦点を当て、「お帰りになられました」がなぜ間違いとされるのかという構造的な問題から、正しい尊敬語・謙譲語の使い分け、ビジネスメールや電話応対での具体的な例文、さらには「行く」や「いる」など移動・所在を示す類語との使い分けに至るまで、この「帰る」の敬語ルールを深く掘り下げて解説いたします。
「帰る」の敬語の構造:尊敬語と謙譲語の基本
まず、「帰る」という動詞に対する尊敬語と謙譲語の基本的な構造を理解し、誰の動作にどの敬語を使うべきかという「敬意の方向性」を明確にしましょう。
相手の動作を高める尊敬語
相手(上司、お客様など)が帰る動作に敬意を払うには、尊敬語を使います。主な表現は以下の三つです。
- 1. お(ご)+動詞の連用形+「になる」最も一般的な尊敬語の作り方です。「帰る」に適用すると「お帰りになる」となります。
- 2. 特殊な尊敬語(敬語動詞)動詞そのものが尊敬の意味を持つ敬語動詞に置き換えます。「帰る」には、尊敬語として「いらっしゃる」(行く、来る、いるの尊敬語を兼ねる)や「お見えになる」が状況によって使われます。
- 3. 助動詞「れる」「られる」動詞に「れる」や「られる」を付けて尊敬の意味を加えます。「帰られる」となりますが、この形はやや敬意が低い、または話し手の地域や世代によっては丁寧語の響きを持つため、ビジネスでは「お帰りになる」を推奨します。
自分の動作をへりくだる謙譲語
自分(話し手)が帰る動作をへりくだって伝えることで、相手に対する敬意を示します。
- 特殊な謙譲語(敬語動詞)「帰る」には、直接的な謙譲語は存在しないため、移動全体を表す「行く」の謙譲語である「失礼する」や「退去する」といった表現を使います。
- 連用形+「ます」謙譲語がないため、「帰ります」という丁寧語を使うのが一般的です。ただし、相手への配慮を示す「お先に失礼いたします」という言い回しを伴うことが多いです。
「お帰りになられました」が間違いとされる構造
多くの方が使ってしまう「お帰りになられました」は、なぜ不適切な表現、または過剰な表現とされるのでしょうか。それは、一つの動作に二重に尊敬語の要素が重ねられているためです。
二つの尊敬語が重なる「二重敬語」
「お帰りになられました」を分解すると、以下のようになります。
- 一つ目の尊敬語要素:「お帰りになる」「お(ご)〜になる」という尊敬語の形です。(帰る+お+連用形+になる)
- 二つ目の尊敬語要素:「〜られた」尊敬の助動詞「られる」が過去形「られた」として付いています。
正しい表現への修正
「お帰りになる」という尊敬語に、さらに尊敬の助動詞「られる」を重ねており、これが「二重敬語」に該当します。この場合は、どちらか一方の尊敬語のみを使うのが正しいとされます。
- 最も正しい形:「お帰りになりました。」(「お帰りになる」+丁寧語「ます」の過去形)
- 許容される形:「帰られました。」(「帰る」+尊敬の助動詞「られる」の過去形)
「帰る」の敬語の正しい使い方と実践的な例文
二重敬語を避け、適切な敬意を込めた「帰る」の敬語表現を、具体的なビジネスシーンで確認しましょう。
相手(お客様・上司)の帰宅を伝える・尋ねる場合
主語が相手であるため、尊敬語を用います。「お帰りになる」を使うのが最も一般的で、丁寧です。
使用例:電話応対や社内報告
- 過去の動作を伝える:「田中部長は、先ほど会議室からお帰りになりました。」
- 現在の状況を尋ねる:「お客様は、もうお見えになりましたか(お帰りになりましたか)?」
- 相手に帰宅を促す:「本日はこれで失礼いたします。お帰りになってお休みください。」
自分(話し手)が帰宅する旨を伝える場合
主語が自分であるため、謙譲語を使います。ただし「帰る」の謙譲語はないため、「失礼する」という動作に謙譲語を適用します。
使用例:退社時や面会終了時
- 「本日はこれで失礼いたします。」(「する」の謙譲語「いたす」を使用)
- 「誠に恐縮ですが、わたくしはここで失礼させていただきます。」(相手の許可を得て、恩恵を受けるニュアンスを込める)
応用と類語の使い分け:「行く」「いる」の敬語との関係
「帰る」は、しばしば「行く」「来る」「いる」といった、移動や所在を示す他の動詞と混同して使われがちです。これらの関連性の高い動詞の敬語も理解しておくことで、より盤石な敬語術を身につけることができます。
「帰る」と「いらっしゃる」の使い分け
「いらっしゃる」は、「行く」「来る」「いる」のすべてをカバーする非常に便利な尊敬語です。「帰る」の尊敬語としても使われることがありますが、帰宅が明確な場合は「お帰りになる」の方がより直接的です。
使用例
- 「お客様は、もうお部屋にいらっしゃいますか。」(いるの尊敬語)
- 「お客様は、もうお帰りになりましたか。」(帰るの尊敬語)
「帰る」の謙譲表現を豊かにする
自分の退室を伝える際、「失礼いたします」だけでは味気ないと感じる場合は、より丁重な表現を検討します。
「退室いたします」などの利用
フォーマルな会議や重役の部屋などから退く際、「退室する」に謙譲語を適用することで、丁寧さを増します。
- 「それでは、ここで退室させていただきます。」
敬語を使う際の心構えと実践的なポイント
「帰る」の敬語を使いこなすための最後の仕上げとして、実践的な心構えと、二重敬語を避けるための簡単なチェック方法をご紹介します。
二重敬語を避けるためのチェックリスト
二重敬語を避けるための基本は、「一つの言葉に、尊敬語は一つまで」というルールを徹底することです。
- 確認手順1:「お(ご)〜になる」の形を使ったら、「られる」や「なされる」は付けない。
- 確認手順2:特殊な尊敬語(例:いらっしゃる、おっしゃる)を使ったら、その前後に「お(ご)」や「られる」は付けない。
実践例:「帰る」を尊敬語にする
- 「お帰りになる」+「ます」=「お帰りになります」 (正しい)
- 「帰る」+「られる」+「ます」=「帰られます」 (正しい)
「内」と「外」の意識を持つ
社外の人に対して自分の上司の帰宅を伝える場合は、「帰られました」といった尊敬語ではなく、謙譲の意を込めた丁寧語を使うのが一般的です。社外の人に対しては、自分の上司も「身内」としてへりくだるためです。
- 社内の人に伝える場合:「部長はお帰りになりました。」
- 社外の人に伝える場合:「部長は、本日帰りました。」(「帰宅いたしました」なども可能)
まとめ:洗練された敬語で信頼を深める
「お帰りになられました」という表現が不適切とされる理由は、敬意を過剰に重ねた「二重敬語」にあることがご理解いただけたかと思います。「帰る」という日常的な動作の敬語を正しく使いこなすことは、細部にまで配慮が行き届いた、洗練されたビジネスパーソンであることの証明になります。
この記事を読んでいただきありがとうございました。