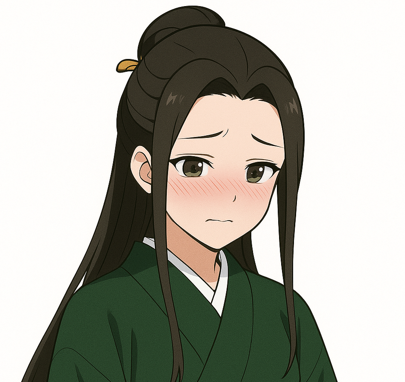「承知いたしました」「了解しました」の正しい使い分けとビジネスメールでの活用法
上司や取引先からの指示や連絡に対し、あなたは普段どのように返信していますか?
「了解です」「承知しました」「わかりました」…これらの返答は、一見同じ意味のようですが、ビジネスシーンでは相手との関係性によって、適切な言葉遣いが厳密に求められます。
特に「承知いたしました」と「了解しました」の使い分けに迷い、どちらを使うべきか一瞬戸惑ってしまう経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
本記事では、この二つの返答を軸に、「わかった」を意味する敬語表現を徹底解説します。それぞれの言葉が持つ敬意の度合いから、NGな使い方、そして応用的な「かしこまりました」との違いまで、具体的な例文とともにご紹介します。この記事を読めば、もう返信に迷うことはなくなり、スマートなビジネス対応が可能になるでしょう。
1. 「承知いたしました」とは?謙譲語としての役割
「承知いたしました」は、動詞「承知する」に謙譲語の「いたす」と丁寧語の「ました」を組み合わせた表現です。「わかった」という自分の動作をへりくだって伝える、非常に丁寧な敬語表現です。
1-1. 「承知」の基本的な意味と敬意の度合い
「承知」は、「知っている」「聞き入れる」という意味を持ち、相手の意向や状況を受け入れ、理解したことをへりくだって伝えます。
謙譲語であるため、相手を立てる意識が強く、ビジネスシーンでは最も適切な返答の一つとされます。
1-2. 「承知いたしました」を使うべき相手とシーン
「承知いたしました」は、主に以下のようなシーンで使われます。
- 社外の取引先や顧客からの依頼、指示への返答
- 社内の上司や役員など、目上の方からの指示、報告への返答
- 改まったビジネスメールや文書での返答
(例文)「ご提案の内容、確かに承知いたしました。準備を進めます。」
(例文)「資料を拝見いたしました。内容について承知いたしました。」
2. 「了解しました」とは?丁寧語としての役割
「了解しました」は、動詞「了解する」に丁寧語の「しました」を組み合わせた表現です。「わかった」という動作を丁寧に伝える言葉です。
2-1. 「了解」の基本的な意味と敬意の度合い
「了解」は、「事情を理解する」「内容を認める」という意味を持ちます。「知る」を丁寧にした言葉であり、謙譲語ではありません。したがって、「承知いたしました」に比べて敬意の度合いは低くなります。
2-2. 「了解しました」を使うべき相手とシーン
「了解しました」は、丁寧語としては正しい表現ですが、目上の人に対して使うと、相手によっては「失礼だ」「配慮が足りない」と感じられる可能性があります。
- 社内の同僚や部下、後輩からの連絡への返答
- 親しい間柄の上司や先輩とのカジュアルな会話
(例文)「スケジュール変更の件、了解しました。」
(例文)「タスクの件、了解しました。早速取り掛かります。」
3. 【実践】「承知」と「了解」の使い分けとNGパターン
二つの表現の基本的な違いを踏まえた上で、ビジネスの現場で迷わないための明確な使い分けルールと、避けるべきNGパターンを解説します。
3-1. 使い分けの絶対ルール:相手への敬意が最も重要
目上の人や取引先に対しては、必ず謙譲語である「承知いたしました」または後述の「かしこまりました」を使いましょう。これがビジネスの基本マナーです。
| 相手 | 最適な表現 | NGまたは避けるべき表現 |
|---|---|---|
| 取引先、顧客、社内の目上 | 承知いたしました / かしこまりました | 了解しました / 了解です / わかりました |
| 社内の同僚、部下 | 了解しました / わかりました | 承知いたしました(丁寧すぎる場合がある) |
3-2. 【NGパターン】目上の人に「了解です」を使う
「了解です」は「了解しました」の「しました」を「です」に言い換えた形であり、丁寧語としてもやや不十分な表現です。特に目上の人に対しては失礼にあたりますので、絶対に避けましょう。
- NG例:「(部長へ)資料作成の件、了解です。」
- OK例:「(部長へ)資料作成の件、承知いたしました。」
3-3. 【NGパターン】「承知しました」は適切か?
「承知しました」は「承知いたしました」よりもやや簡略化された表現です。間違いではありませんが、より丁寧さが求められる取引先や非常に厳格な上司に対しては、謙譲語「いたす」を加えた「承知いたしました」を選ぶのが無難です。
4. 応用表現:「かしこまりました」と「わかった」の丁寧な表現
「承知いたしました」と並んでよく使われる「かしこまりました」や、カジュアルな「わかった」の丁寧な言い換え表現を知ることで、語彙力を増やしましょう。
4-1. 「かしこまりました」の意味と使い分け
「かしこまりました」は、「承知いたしました」と同様に「わかった」の謙譲語ですが、「謹んでお受けしました」というニュアンスが強く、相手の要望や依頼を「謹んで引き受ける」という深い敬意を示します。主に接客業やサービス業など、客からの注文や依頼を受ける際に使われます。
- 「承知いたしました」:内容を理解・認識したことを伝える。
- 「かしこまりました」:内容を理解し、その依頼を確かに引き受けたことを伝える。
4-2. 「わかった」を伝える類語表現
状況や相手によっては、「承知いたしました」を多用するよりも、他の表現でスムーズに返答する方が好ましい場合があります。
- 「承知いたしました」の言い換え:「拝命いたしました」(特に重要な命令や役目を引き受けた際)
- 「了解しました」の言い換え:「確認いたしました」(内容をチェックしたことを伝える)
5. ビジネスメールでの効果的な使い方
メールでの返信では、「承知いたしました」に一言添えることで、より丁寧で心遣いのある対応に見えます。
5-1. 確認事項を添えて返答する
単に「承知いたしました」と伝えるだけでなく、何を承知したかを具体的に添えることで、認識のズレを防ぎます。
- 「納期の変更の件、承知いたしました。〇月〇日までに必ず提出いたします。」
5-2. 感謝を添えて依頼を受ける
依頼や指示を受けたことに対し、感謝の意を伝えることで、相手に好印象を与えます。
- 「ご丁寧にご指示いただき、承知いたしました。ありがとうございます。」
まとめ
本記事では、「承知いたしました」と「了解しました」の厳密な違いと、ビジネスシーンでの正しい使い分けを解説しました。
最も重要な使い分けのルールは、相手への敬意の度合いです。
- 社外・目上の方へは:謙譲語である「承知いたしました」または「かしこまりました」
- 社内の同僚・目下へは:丁寧語である「了解しました」または「わかりました」
この基本を徹底することで、あなたのビジネスコミュニケーションはより洗練されたものになり、信頼度が向上するでしょう。この記事を参考に、自信を持って適切な敬語を使いこなしてください。
この記事を読んでいただきありがとうございました。