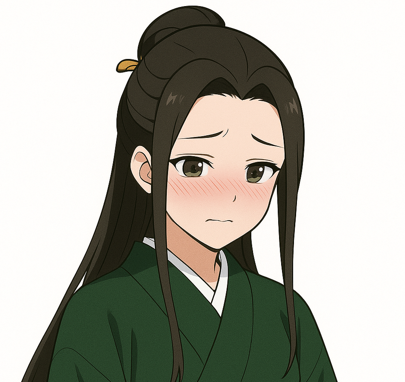上司からの指示や依頼を受けた際、私たちの多くは「承知いたしました」という返事をします。これは、相手の指示を「謹んで受け止めた」ことを示す正しい謙譲表現であり、ビジネスマナーの基本です。
しかし、どのような指示に対しても、毎回「承知いたしました」とだけ返していては、「単に指示を受け取っただけ」という、やや受動的で機械的な印象を与えてしまう可能性があります。一方で、「デキる」と評価されるビジネスパーソンは、この返事一つで、指示への深い理解、実行への積極性、そして「この人に任せれば大丈夫だ」という安心感を上司に与えています。
本記事では、「承知いたしました」という基本の返事を一歩超え、上司に一目置かれる「デキる返事」とは何かを構造的に分析します。さらに、その場ですぐに使える、あなたの信頼度を高める10個の言い換え・付加フレーズを、具体的な例文とともにご紹介します。
「承知」が持つ構造と「デキる返事」に必要な要素
まず、「承知いたしました」という言葉が持つ基本的な構造と、なぜそれだけでは不十分な場合があるのかを分析します。
「承知いたしました」の構造分析
「承知」は、「事情や依頼などを聞き知ること」を意味し、それに「いたす(するの謙譲語)」「ました(丁寧語)」がついています。つまり、その中核的な意味は「謹んで(あなたの指示を)受け取り、理解しました」という受領の報告です。
これは文法的に完璧な敬語ですが、あくまで「受け取った」という過去・完了の報告に留まります。上司が本当に知りたいのは、「受け取ったか」どうかよりも、「(受け取った上で)それをどう実行し、どう完遂してくれるのか」という未来の行動です。
「デキる返事」に必要な三つの要素
上司に一目置かれる「デキる返事」とは、「承知いたしました」という受領報告に、以下の三つの要素のうち少なくとも一つが加えられたものです。
- 積極性(Proactivity): 「受け取ったので、すぐに行動します」という意欲。
- 具体性(Specificity): 「受け取った内容を、このように理解し、この手順で進めます」という、指示の正確な理解。
- 責任感(Responsibility): 「受け取った任務を、最後までやり遂げます」という、相手を安心させるコミットメント。
この三要素を加えることで、あなたの返事は「受領報告」から、「(この件はもう私にお任せくださいという)安心感の提供」へと進化します。
上司に一目置かれる「デキる返事」フレーズ10選
ここからは、「承知いたしました」の代わり、あるいはそれに付加することで、あなたの評価を格段に上げる10個のフレーズを、カテゴリ別に解説します。
カテゴリ1:積極性とスピード感を伝える(Proactivity)
指示に対して、即座に行動する姿勢を見せることで、意欲とスピード感をアピールします。
1. かしこまりました
「承知いたしました」の、より丁寧で「相手の意向を謹んで受け入れる」というニュアンスが強い代替表現です。特に、お客様や上位の役職者からの指示に対して、即座に「Yes」と返答する際に最適です。
例文:「かしこまりました。そのように手配いたします。」
2. 承知いたしました。ただちに着手いたします
「承知」に「ただちに(すぐに)」という言葉を加えることで、指示の優先順位を上げ、即座に行動に移すという積極性を示します。上司に「この件はすぐに動いてほしい」という意図がある場合に最も響く返事です。
例文:「(急ぎの依頼に対し)承知いたしました。ただちに着手いたします。」
3. 承知いたしました。まず、〇〇から進めます
複数の指示や、複雑な依頼を受けた際に有効です。「承知」した上で、自分が理解した「最初の一手(優先順位)」を宣言することで、上司は「あ、この人は正しく理解し、手順立てもできているな」と安心できます。
例文:「承知いたしました。まず、A社へのアポイント調整から進めます。」
カテゴリ2:正確な理解と配慮を示す(Specificity)
指示の背景や懸念点を正確に理解していることを示し、ミスを防ぐ能力をアピールします。
4. 承知いたしました。〇〇という認識でよろしいでしょうか
これは、指示が曖昧な場合や、絶対に失敗が許されない場面で最強の「デキる返事」です。指示をオウム返しするのではなく、自分の言葉で要約し、認識が正しいかを確認することで、実行後の「思っていたのと違う」という最悪の事態を未然に防ぎます。
例文:「承知いたしました。要するに、今回はコストよりも納期優先という認識でよろしいでしょうか。」
5. (ご懸念について)承知いたしました。その点は留意(クリア)して進めます
上司が指示と共に「〇〇だけは気をつけてくれ」といった懸念点を示した場合、その懸念点をしっかり受け止めたことを示す返事です。「承知しました」だけでは、その懸念が伝わったか不安になりますが、この一言で「リスク管理も任せられる」と評価されます。
例文:「承知いたしました。競合の動きには留意して進めます。」
6. (ご指示)拝承(はいしょう)いたしました
「拝承」は「承知」のさらに丁寧な謙譲語で、主に書き言葉(メール)で使われます。「謹んで拝聴し、承りました」という、非常に高い敬意を示します。重要なプロジェクトの依頼メールへの返信などに使うと、事の重大さを理解していることが伝わります。
例文:「(メールで)プロジェクトリーダー就任の件、拝承いたしました。身の引き締まる思いです。」
カテゴリ3:責任感と完遂力を示す(Responsibility)
「この件はもう心配いりません」という、強い責任感と安心感を与える返事です。
7. お任せください
自信の表れであり、上司に最も強い安心感を与える言葉の一つです。ただし、自分の能力や経験を明らかに超えることに対して使うと、無責任や傲慢と受け取られるリスクもあります。自分が得意とする分野や、確実に完遂できるタスクに対して、力強く使いましょう。
例文:「(得意分野の資料作成を頼まれ)お任せください。明日の朝までにご用意します。」
8. 承知いたしました。責任を持って対応いたします
「お任せください」ほどの自信はないが、強い責任感を示したい場合に最適です。「責任を持って」という言葉が、上司の「(最後までやってくれるかなという)不安」を打ち消します。
例文:「(他部署との調整など)承知いたしました。責任を持って対応いたします。」
9. (難しい指示に対し)万全を尽くします
成功が100パーセント保証できない、困難な指示を受けた際の返事です。「できます」と安請け合いするのではなく、「(結果はともかく)できる限りの全ての準備と努力をします」という誠実さと責任感を示します。
例文:「(厳しい交渉を命じられ)承知いたしました。万全を尽くします。」
10. 確かに(ご指示)承りました
「承る(うけたまわる)」は「受ける」の謙譲語で、指示や注文を謹んで受ける際に使います。「確かに」と合わせることで、「あなたの指示を、私は確かに引き受けました」という、受諾の意思を強く示すことができます。
例文:「確かに承りました。ご期待に沿えるよう尽力いたします。」
類語との使い分けと使用上の注意点
「デキる返事」を目指す上で、絶対に避けるべき言葉と、注意点を解説します。
絶対NG:「了解しました」
「承知」と「了解」の使い分けは、ビジネスマナーの基本です。
- 了解(りょうかい): 「事情を理解し、認める」という意味です。ここには謙譲(へりくだる)のニュアンスが含まれておらず、目上の人が目下の人に使う、あるいは同僚同士で使う言葉です。
- 承知(しょうち): 「(相手の意向を)謹んで受け止める」という謙譲のニュアンスが含まれます。
上司に対して「了解しました」と返事をすることは、相手を同等以下と見なしていると受け取られ、非常に失礼にあたります。必ず「承知いたしました」または「かしこまりました」を使いましょう。
「お任せください」の多用は禁物
前述の通り、「お任せください」は強力な言葉ですが、多用すると信頼を失います。根拠のない自信は、無責任の裏返しです。自分のスキルセットと納期を冷静に判断し、ここぞという場面で使いましょう。
まとめ:「デキる返事」とは「信頼」を築く返事である
上司からの指示に対する返事は、単なる「YES/NO」の確認作業ではありません。それは、上司との信頼関係を築くための、重要なコミュニケーションの瞬間です。
「承知いたしました」という正しい基本を大切にしつつ、そこに「積極性」「具体性」「責任感」という要素を一つまみ加えること。本記事で紹介した10のフレーズは、そのための具体的な道具です。
あなたの返事一つで、上司に「この件は、もう彼(彼女)に任せて大丈夫だ」という安心感を与えることができれば、あなたの評価は確実に「一目置かれる」存在へと変わっていくでしょう。
この記事を読んでいただきありがとうございました。