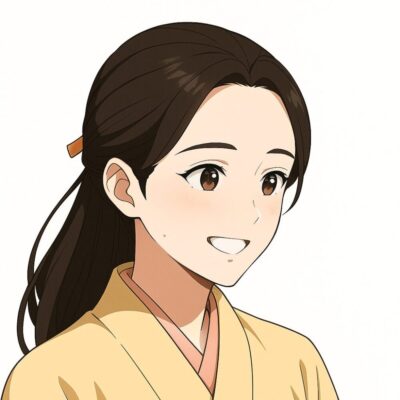会社の受付や、お客様をお迎えする立場にある時、その対応は会社の「顔」として、相手に与える印象を大きく左右します。お客様が到着された際、社内の担当者へその到着を伝える「取り次ぎ」の場面は、正しい敬語が最も厳しく求められる瞬間の一つです。
その際、お客様の到着を知らせるために「〇〇様がお見えになりました」というフレーズが使われます。この表現は、一見すると「お」と「なる」が使われており、二重敬語ではないか、あるいは使い方が正しいのかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「お見えになりました」は、来客を知らせる際の敬語として、実は非常に適切で格調高い表現です。本記事では、「お見えになりました」という表現の敬語構造を深く掘り下げ、なぜこれが正しいのかを解説します。さらに、来客時の取り次ぎマナーとして、失礼のない具体的な使い方や、よくある間違いやすい類語との比較を、例文とともにご紹介します。
「お見えになりました」の敬語構造と分析
まず、「お見えになりました」という表現が、日本語の敬語の中でどのように位置づけられているのか、その構造を分析します。このフレーズが二重敬語だと誤解されることがありますが、その理由と、それが間違いである根拠を見ていきましょう。
「お見えになる」が持つ敬意の構造
「お見えになりました」は、「お見えになる」という尊敬語の過去形です。この「お見えになる」は、以下の二つの動詞に対する尊敬語として機能します。
- 1. 「来る」(くる)の尊敬語
- 2. 「いる」(いる)の尊敬語
「来る」の尊敬語としては「いらっしゃる」も一般的ですが、「お見えになる」は、特に「相手が(こちらに)姿を見せる」という「到着」のニュアンスを明確に持つ表現です。来客の到着を伝える場面において、これ以上ないほど的確な尊敬語と言えます。
なぜ二重敬語と誤解されるのか
この表現が二重敬語と誤解される原因は、「見える」という動詞の存在にあります。
「見える」という動詞に、尊敬語の公式である「お〜になる」を付け加えて「お見えになる」とすると、「見(え)る」+「お〜になる」で二重敬語のように見えてしまいます。
しかし、ここで使われている「お見えになる」は、そのような成り立ちではありません。「お見えになる」は、それ自体で「来る」の尊敬語として確立された、一つの単語(連語)です。したがって、これは二重敬語ではなく、文法的に完全に正しい、敬意の非常に高い表現です。
「お見えになりました」の正しい使い方と文脈
「お見えになりました」は、社内の担当者(上司や同僚)に対して、お客様の到着を報告・連絡する「取り次ぎ」の場面で最も効果を発揮します。
来客の取り次ぎ(内線・社内報告)
受付担当者や、最初にお客様に応対した社員が、担当者本人に連絡する際に使用します。この時、主語はお客様であり、そのお客様の「来た」という行為を最大限に高めて表現しています。
使用例:内線電話での報告
「お疲れ様です。受付の佐藤です。ABC商事の田中様がお見えになりました。応接室にご案内いたします。」
使用例:上司への口頭報告
「課長、先ほどアポイントメントの山田様がお見えになりました。現在、第一応接室でお待ちいただいております。」
お客様へ直接の使用は避ける
「お見えになりました」は、第三者(社内の人間)に対して、お客様の到着を報告する際に使うのが基本です。お客様本人に向かって「ようこそ、お見えになりました」と使うことは文法的に間違いではありませんが、一般的ではありません。
お客様本人にかける言葉としては、「ようこそおいでくださいました」「お待ちしておりました」といった歓迎の言葉の方が、より自然で心のこもった挨拶となります。
失礼のない取り次ぎマナーと応用表現
「お見えになりました」という言葉を使う前後の行動や、その他の表現を知っておくことで、よりスムーズで失礼のない取り次ぎが可能になります。
お客様をお待たせする場合の対応
担当者がすぐに来られない場合、お客様を待たせてしまうことになります。その際は、まずお客様に対して丁寧にお詫びと状況説明を行います。
お客様への対応例:
「誠に恐れ入ります。ただいま担当者の鈴木が参りますので、恐縮ですが、こちらの応接室で少々お待ちいただけますでしょうか。」
担当者への報告(応用)
単に到着を伝えるだけでなく、お客様の様子や、どこでお待ちいただいているかを正確に伝えることが、社内の円滑な連携に繋がります。
担当者への報告例:
「お疲れ様です。ABC商事の田中様がお見えになりました。恐れ入りますが、ただいまお電話中のようですので、終わり次第、応接室にご案内いたします。」
類語との使い分けと「取り次ぎ」の注意点
「来る」の尊敬語には他にもあり、特に取り次ぎの際には謙譲語との混同が起こりやすいため、注意が必要です。
「いらっしゃいました」との違い
「いらっしゃる」も「来る」の尊敬語であり、「〇〇様がいらっしゃいました」も、取り次ぎの言葉として全く間違いではありません。
- 「お見えになりました」: 「姿を見せる」「到着する」というニュアンスが強く、来客の報告として非常に明確です。格調高く、フォーマルな印象を与えます。
- 「いらっしゃいました」: 「来る」「行く」「いる」の全てをカバーする万能な尊敬語です。「お見えになりました」よりも、やや柔らかい印象を与える場合があります。
どちらも正しい敬語ですが、企業の受付など、より厳格な敬語が求められる場面では「お見えになりました」が好まれる傾向があります。
絶対的な誤用:「参られました」
取り次ぎにおいて、最も注意すべき間違いが「〇〇様が参られました」という表現です。
- 「参る(まいる)」: 「来る」「行く」の謙譲語です。自分や、自分の身内(社内の人間)の行為をへりくだる時に使います。(例:「私が参ります」「担当者の鈴木が参ります」)
- 「参られました」: この謙譲語「参る」に、尊敬語の助動詞「られる」を付け足したもので、謙譲語と尊敬語が混在した二重敬語の誤用です。お客様の行動に対して謙譲語を使うこと自体が、根本的な間違いとなります。
お客様の到着を伝える際は、必ず「お見えになりました」または「いらっしゃいました」という尊敬語を使いましょう。
まとめ:敬意を込めた取り次ぎで信頼を築く
「お見えになりました」という表現は、二重敬語ではなく、お客様の「到着」という行為に対し、最高の敬意を払うための正しい尊敬語です。
この言葉は、お客様本人に直接使うのではなく、社内の担当者へお客様の到着を報告する「取り次ぎ」の際に使用するのが最も適切です。来客応対は、その言葉遣い一つで会社の品格が問われる重要な場面です。「お見えになりました」を正しく使いこなし、「参られました」のような誤用を避けることが、お客様への心からのおもてなしと、社内の円滑な連携の第一歩となります。
この記事を読んでいただきありがとうございました。