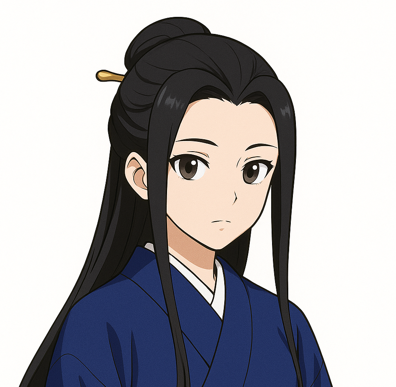ビジネスシーンで、上司や取引先からお褒めの言葉をいただいた時、あるいは感謝の言葉をかけられた時。「いえいえ、とんでもございません」と謙遜の気持ちを込めて返答している方は、とても多いのではないでしょうか。
この「とんでもございません」という表現は、非常に丁寧で、相手への深い敬意を示す言葉として、社会に広く浸透しています。しかしその一方で、この言葉は「文法的には間違っている」「日本語として不自然だ」と指摘されることが、昔から非常に多い表現でもあります。
せっかく相手への感謝や謙遜の気持ちを伝えようと選んだ言葉が、もし「正しい日本語を知らない」という印象を与えてしまったとしたら、それはとても残念なことです。
果たして、「とんでもございません」はビジネスシーンで使っても良いのでしょうか、それとも避けるべきなのでしょうか。この記事では、この言葉がなぜ議論の的になるのか、その文法的な背景を優しく紐解きながら、文化庁が示す現代の解釈、そしてビジネスの場で自信を持って使える「とんでもない」の正しい使い方や、スマートな言い換え表現について、一緒に確認していきたいと思います。
「とんでもございません」が「間違い」とされる文法的な理由
まずはじめに、なぜ「とんでもございません」という、一見すると丁寧な言葉が「間違いだ」と指摘されてしまうのか、その理由を見ていきましょう。答えは、「とんでもない」という言葉の成り立ちに隠されています。
「とんでもない」は、一つの「形容詞」
伝統的な文法解釈において、「とんでもない」という言葉は、「とんでも」と「ない」に分解できる言葉ではありません。これは、「みっともない」「もったいない」「せわしない」といった言葉と同じ仲間で、「とんでもない」という一続きで、一つの「形容詞」として扱われてきました。
例えば、私たちは「赤い」という形容詞を丁寧にするとき、「赤ございません」とは言いませんよね。「赤いです」や「赤くありません(ございません)」と活用させます。
これと同じルールを当てはめると、「とんでもない」の「ない」の部分だけを抜き出して「ございません」に置き換えた「とんでもございません」という形は、文法的に不自然である、とされてきたのです。
伝統的な正しい活用とは
もし、この伝統的なルールに厳格に従うならば、「とんでもない」を丁寧に表現する場合は、以下のようになります。
- 「とんでもないです」
- 「とんでもないことでございます」
このような背景から、特に言葉遣いに厳しい方や、伝統的な日本語の美しさを重んじる方にとっては、「とんでもございません」は違和感のある「誤った日本語」と聞こえてしまうのです。
時代の変化?文化庁が示す「許容」という見解
文法的には「誤り」とされる一方で、現実の社会では「とんでもございません」という表現が、ビジネスメールや接客の現場で溢(あふ)れています。このねじれについて、国の文化審議会(文化庁)は、平成19年に「敬語の指針」という一つの見解を示しています。
「とんでもない」の新しい解釈
文化庁の指針では、もちろん先に述べた「とんでもない、で一つの形容詞」という伝統的な解釈が基本であると説明しています。
しかし同時に、現代の言葉の使い方として、「申し訳ない」を「申し訳ございません」と表現したり、「情けない」を「情けなく存じます」と表現したりするように、「とんでもない」も「とんでも」と「ない」に分けて認識されるようになってきている、という現実にも触れています。
文化庁が示した「許容」という結論
そして、結論として、「とんでもございません(あるいは、とんでもありません)」という表現は、相手からの褒め言葉や賞賛などを強く謙遜して否定する意図で使われる場合には、**現在では「問題ない」あるいは「許容される」**ものである、と示しているのです。
これは、「とんでもないです」と言うよりも、「とんでもございません」と言ったほうが、より強く、より丁寧に謙遜の気持ちを伝えられる、と感じる人が大多数になった結果、社会的に定着した表現として認められた、ということになります。
【シーン別】「とんでもない」の正しいビジネスでの使い方
これで、「とんでもございません」は、現代のビジネスシーンで使っても差し支えない表現である、ということが分かりました。ただし、伝統的な文法を知る人への配慮や、より洗練された言葉遣いを目指す上では、他の表現も知っておくことが大切です。
ここでは、具体的なシーン別に、適切な使い方と、より望ましい表現を比較してみましょう。
シーン1:相手からの賞賛や褒め言葉を謙遜する時
相手:「〇〇さんのプレゼン、本当に素晴らしかったですね。」
許容される表現(現代的)
「とんでもございません。皆様にご協力いただいたおかげでございます。」
より丁寧・伝統的な表現
「とんでもないことでございます。まだまだ勉強不足でございます。」
「滅相(めっそう)もございません。〇〇様のご指導のおかげです。」
シンプルな表現
「恐れ入ります。そのように仰っていただき、光栄に存じます。」
「恐縮でございます。皆様のお力添えに感謝いたします。」
シーン2:相手からの感謝の言葉に「どういたしまして」と返す時
相手:「資料をまとめていただき、本当に助かりました。ありがとうございます。」
許容される表現(現代的)
「とんでもございません。お役に立てて幸いです。」
より望ましい表現
「お役に立てて、何よりでございます。」
「喜んでいただけて幸いです。」
「(相手が目上すぎない場合)どういたしまして。」
この場面での「とんでもございません」は、少し謙遜が強すぎる印象を与える場合もあります。「お役に立てて嬉しい」という素直な気持ちを伝えるほうが、相手も安心することがあります。
シーン3:相手からの謝罪に「気にしないでください」と返す時
相手:「納期が遅れてしまい、誠に申し訳ございません。」
許容される表現(現代的)
「とんでもございません。どうぞ、お気になさらないでください。」
より望ましい表現
「いえいえ、滅相もないことでございます。」
「どうぞ、お気になさらないでくださいませ。」
「(状況を理解している場合)大変な中、ご対応いただきありがとうございます。」
シーン4:事実と全く異なる誤解を強く否定する時
相手:「(誤解して)このミスは、〇〇さんのご担当でしたか?」
この場面での「とんでもない」は、謙遜ではなく「全く違います」「滅相もない」という強い否定の意図で使われます。
望ましい表現
「いえ、とんでもないことでございます。そのような事実はございません。」
「滅相もございません。こちらは〇〇(部署名など)の管轄でございます。」
この場合、「とんでもございません」だけを単体で使うと、謙遜なのか否定なのかが曖昧になり、相手に意図が伝わりにくくなる可能性があります。「とんでもないことです」や「滅相もございません」と、はっきりと否定する言葉を選ぶほうが明確です。
よりスマートに!「とんでもない」の言い換え表現集
「とんでもございません」は許容されているとはいえ、やはり言葉の背景を知る人にとっては、少しだけ違和感が残る表現でもあります。特に、格式の高い相手や、非常にフォーマルな場では、より正確で洗練された言葉を選ぶ配慮が、あなたの印象をさらに高めます。
謙遜の気持ちを伝えたい時の言い換え
- 「恐れ入ります」
- 「恐縮でございます」
- 「(お褒めいただき)光栄に存じます」
- 「滅相もございません」(「とんでもない」よりも、さらに強く謙遜・否定する言葉です)
感謝への返答(どういたしまして)の言い換え
- 「お役に立てて幸いです」
- 「お役に立てて何よりでございます」
- 「こちらこそ、ありがとうございます」(相手の協力に感謝を返す場合)
謝罪への返答(気にしないで)の言い換え
- 「どうぞ、お気になさらないでください」
- 「(こちらこそ)お力になれず申し訳ございません」
- 「ご丁寧にありがとうございます」(謝罪の言葉自体に感謝を返す場合)
まとめ:言葉の背景を知り、心を込めて使い分ける
「とんでもございません」という言葉は、伝統的な文法では「間違い」とされてきましたが、謙遜の気持ちをより強く、より丁寧に伝えたいという人々の思いから、現代では広く「許容」される表現となりました。
ビジネスパーソンとして大切なのは、この言葉を思考停止で使うことではなく、「なぜこの言葉が議論になるのか」という背景をきちんと理解することです。その上で、あえて「とんでもございません」という柔らかい表現を選ぶのか、それとも「恐れ入ります」や「とんでもないことでございます」といった、より伝統的で正確な表現を選ぶのか。
その場にいる相手や、状況、そしてご自身が伝えたい謙遜の度合いに合わせて、最適な言葉を選び分けることができることこそが、本当の意味での「相手への配慮」であり、洗練されたコミュニケーションと言えるのではないでしょうか。
言葉の持つ歴史やニュアンスを大切にしながら、心を込めて使い分けてみてくださいね。
この記事を読んでいただきありがとうございました。