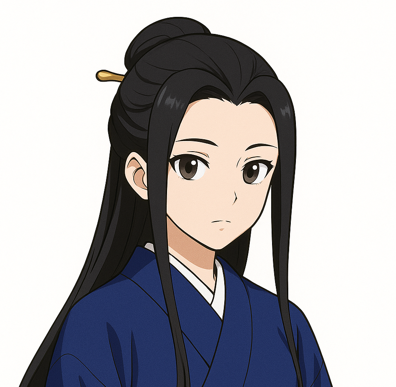ビジネスシーンや公的な場面で、非常に頻繁に耳にする「〜させていただきます」という表現。例えば、「資料をお送りさせていただきます」「本日は休ませていただきます」「ご説明させていただきます」といった具合です。非常に丁寧な印象を与える便利な言葉として広く使われる一方で、「何でもかんでも『させていただく』がついていて違和感を覚える」「日本語として本当に正しいのか」といった指摘や、「させていただく病」と揶揄されるほどの過剰な使用に対する懸念の声も聞かれます。
相手に失礼がないように、と配慮した結果として使われることが多いこの表現ですが、果たして本当に「正しい敬語」なのでしょうか。あるいは、どのような場合に「間違い」や「不適切」となってしまうのでしょうか。
実は、この「〜させていただく」という表現については、国の文化審議会が答申し、文化庁が取りまとめた「敬語の指針」(平成19年)において、その適切な使用条件が具体的に示されています。
本記事では、この文化庁の指針に基づき、「〜させていただく」の基本的な構造から、正しいとされる使い方、そして避けるべき不適切な使用例までを、深く掘り下げて解説いたします。この機会に、つい使ってしまいがちな「〜させていただく」の正しいルールを再確認してみませんか。
「〜させていただく」の基本的な構造と敬語分類
まず、「〜させていただく」という言葉が、どのような文法的な要素で構成されているのか、そして敬語としてどのように位置づけられるのかを見ていきましょう。
「〜させていただく」を構成する要素
この表現は、大きく分けて二つの要素から成り立っています。
1. 使役の助動詞「(さ)せる」
動詞の後につき、「〜(さ)せる」という形で、他からの許可や指示によってその動作を行う、という意味合いを持ちます。例えば「(相手が私に)説明させる」というニュアンスです。
2. 補助動詞「いただく」
「いただく」は、「もらう」の謙譲語です。「〜してもらう」の謙譲表現として「〜ていただく」という形で使われ、相手(あるいは第三者)から何らかの恩恵や許可を受けることを、へりくだって表現します。
敬語としての位置づけ
これら二つが組み合わさることで、「〜させていただく」は、「(相手の許可や恩恵によって)私は〜という動作を行うことを許してもらう」という意味を持つ、非常に丁重な謙譲語表現となります。自分の動作をへりくだり、かつその動作を行うにあたって相手の存在や許可を前提とすることで、相手に対する強い敬意を示す表現として機能します。
この構造を理解することが、なぜ文化庁が特定の「条件」を示すに至ったのかを理解する鍵となります。
文化庁「敬語の指針」が示す2つの条件
「〜させていただく」は、その成り立ちから分かるように、非常に丁寧な表現である一方、その使用には特定の前提が必要です。文化庁の「敬語の指針」では、この表現が適切とされるための条件として、以下の二点を挙げています。
この二つの条件が両方とも満たされている場合、「〜させていただく」の使用は適切であるとされています。
条件1:相手(または第三者)の「許可」が必要な状況
一つ目の条件は、その動作を行うにあたって、相手側(あるいは、その場にいない第三者)からの「許可」が必要である、という状況です。
自分の行動が、何らかの形で相手の領域に関わったり、相手に影響を与えたりする可能性があるため、事前に許可を得る、あるいは許可を得ているという前提に立つ必要がある場面です。
適切な使用例(許可が必要な場合)
- 「(あなたの会社に)明日、伺わせていただきます。」(相手の会社を訪問するには、相手の許可が必要です。)
- 「(あなたの)個人情報を利用させていただきます。」(個人情報を利用するには、本人の許可が不可欠です。)
- 「(会議室を)使わせていただきます。」(共有の会議室を使うには、ルール上の許可や他の利用者の了承が必要です。)
条件2:その許可によって「恩恵」を受けるという事実
二つ目の条件は、その動作(許可を得て行う動作)によって、話し手自身が何らかの「恩恵」を受ける、という事実です。
「〜いただく(もらう)」という謙譲語が使われている以上、相手の許可によって自分が利益や恩恵を受ける、という感謝の気持ちが含まれている必要があります。
適切な使用例(恩恵がある場合)
- 「(ご質問に)回答させていただきます。」(相手から質問という「機会」を与えられ、それに回答できるという恩恵を受けている、と解釈できます。)
- 「(本日は)休ませていただきます。」(本来は働くべきところを、会社の許可によって休むことができ、心身を休めるという恩恵を受けます。)
- 「発表させていただきます。」(大勢の前で発表するという「機会」を与えられ、自分の意見を述べるという恩恵を受けます。)
文化庁の指針によれば、原則としてこの「許可」と「恩恵」の二つが揃ったときに、「〜させていただく」は最も適切で、敬意の度合いが高い表現として機能する、とされています。
「させていただく」の不適切な使い方とは?
問題となるのは、文化庁が示す上記の二つの条件を満たしていないにもかかわらず、「〜させていただく」が多用されてしまうケースです。これが、いわゆる「させていただく病」と呼ばれるものであり、聞き手に違和感や不快感を与えてしまう原因となります。
不適切なケース1:相手の「許可」が不要な場合
自分の動作が、相手の許可を必要としない場面で「〜させていただく」を使うのは不適切です。許可が不要なことにまで許可を求める(かのような)表現を使うと、非常に回りくどく、場合によっては皮肉や慇懃無礼(いんぎんぶれい)と受け取られかねません。
不適切な使用例(許可が不要)
- 「(弊社の新商品を)ご紹介させていただきます。」→(解説)自社の商品を紹介する行為は、相手の許可を前提とするものではありません。「ご紹介いたします」が適切です。
- 「(私は)〇〇と申させていただきます。」→(解説)自分の名前を名乗るのに、相手の許可は不要です。「〇〇と申します」が適切です。
- 「(私は〇〇に)努めさせていただきます。」→(解説)自分が努力することに許可は不要です。「努めてまいります」などが適切です。
これらの例では、話し手自身が行うべき動作、あるいは行うと決めた動作であり、相手の許可を必要としないため、「〜させていただく」は過剰な敬語となります。
不適切なケース2:「恩恵」の要素がない、または薄い場合
動作を行うことで、話し手が恩恵を受けるというよりも、むしろ相手のために行う(奉仕する)というニュアンスが強い場合も、「〜させていただく」は適しません。
不適切な使用例(恩恵がない)
- 「(お客様を)ご案内させていただきます。」→(解説)お客様を案内するのは、サービスを提供する側の当然の行為(奉仕)であり、「恩恵」とは異なります。「ご案内いたします」または「ご案内申し上げます」が適切です。
- 「(荷物を)お持ちさせていただきます。」→(解説)相手の荷物を持つ行為は、相手への配慮や奉仕です。「お持ちいたします」が適切です。
不適切なケース3:単なる丁寧語のつもりでの「乱用」
最も多いのが、上記の条件を深く考えず、単に「〜します」を丁寧にしたつもりの万能な敬語として「〜させていただきます」を乱用してしまうケースです。
不適切な使用例(乱用)
- 「(資料を)拝見させていただきます。」→(解説)「拝見する」自体が謙譲語です。「させていただく」をつけると二重敬語となり、非常にくどい印象を与えます。「拝見いたします」で十分丁寧です。
- 「(明日は)晴れさせていただきます。」→(解説)天候など、人間の意志や許可が関与しない事柄に使うのは明らかな間違いです。
「〜させていただく」の適切な言い換え表現
では、「〜させていただく」が不適切だと判断した場合、どのように言い換えればよいのでしょうか。敬語の基本に立ち返り、状況に応じた適切な表現をご紹介します。
基本の謙譲語:「(お/ご)〜いたします」
「〜させていただく」が過剰となる場面の多くは、この「(お/ご)〜いたします」で自然に言い換えることができます。これは「する」の謙譲語「いたす」を用いた、自分の動作をへりくだる基本的な表現です。
言い換えの例
- 「ご説明させていただきます」 → 「ご説明いたします」
- 「ご紹介させていただきます」 → 「ご紹介いたします」
- 「ご案内させていただきます」 → 「ご案内いたします」
- 「お送りさせていただきます」 → 「お送りいたします」
さらに丁重にする場合:「(お/ご)〜申し上げます」
「いたします」よりもさらに丁重な敬意を示したい場合、特に相手への感謝や恐縮の気持ちを強く込めたい場合は、「申し上げる」(「言う」の謙譲語)を補助動詞として使います。
言い換えの例
- 「(心より)感謝させていただきます」 → 「(心より)感謝申し上げます」
- 「お詫びさせていただきます」 → 「お詫び申し上げます」
- 「お願いさせていただきます」 → 「お願い申し上げます」
自分の意志や決定を伝える場合:「〜いたします」「〜(する)所存です」
相手の許可ではなく、自分の意志として決定した事項を丁寧に伝える場面です。
言い換えの例
- 「(今後は)注意させていただきます」 → 「(今後は)注意いたします」
- 「精一杯、努めさせていただきます」 → 「精一杯、努めてまいる所存です」
相手に了承を求める場合:「〜いたしますので、ご了承ください」
「休ませていただきます」のように、許可を得るニュアンスは必要だが、相手に直接的な恩恵があるわけではない場合(例えば、一方的な通知になってしまう場合)の言い換えです。
言い換えの例
- 「(明日は)休ませていただきます。」→(同僚や取引先への連絡の場合)「(明日は)お休みをいただきます(頂戴します)。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
→(一方的な通知の場合)「誠に勝手ながら、明日は休業いたします。何卒ご了承ください。」
まとめ:敬語の本質は「相手への配慮」
「〜させていただく」という表現は、文化庁の指針にある通り、一概に「間違い」なわけではありません。「相手の許可」と「それによる恩恵」という二つの条件が揃った場面で使えば、相手への深い敬意と感謝を示すことができる、非常に丁寧な表現です。
しかし、この条件を満たさない場面で、単に丁寧さを装うために乱用してしまうと、かえって聞き手に違和感を与え、日本語の乱れとして指摘されてしまいます。特に、許可が不要な自分の行動にまで使用すると、責任の所在を曖昧にしたり、慇懃無礼な印象を与えたりする危険性もはらんでいます。
大切なのは、言葉の形だけを覚えるのではなく、その言葉が持つ本来の意味や構造を理解することです。そして、今この場面で、目の前の相手に対して、どのような敬意(謙譲、尊敬、丁寧)を示すのが最も適切なのかを考えることです。
文化庁の「敬語の指針」は、私たちを縛る厳格なルールというよりも、円滑なコミュニケーションを築くための「道しるべ」です。もし「〜させていただく」を使いそうになったら、一度立ち止まり、「許可は必要か?」「恩恵はあるか?」と自問してみてください。その上で、「〜いたします」や「〜申し上げます」といった他の表現を選ぶことができれば、皆様の敬語はより洗練され、相手の心に響くものになるはずです。
この記事を読んでいただきありがとうございました。