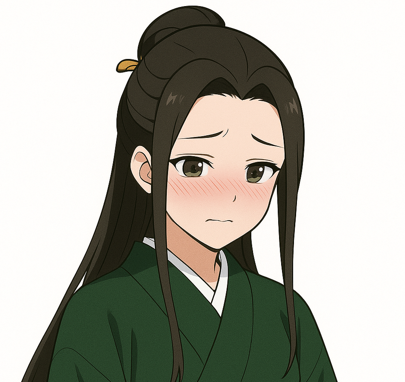会議やセミナー、プレゼンテーションなど、ビジネスの公式な場でイベントの開始を伝える瞬間は、登壇者や主催者にとってとても大切な場面です。このとき、「そろそろ始めます」を丁寧に伝える表現としてよく使われるのが、「開始いたします」と「はじめさせていただきます」の二つです。どちらもイベントのスタートを示す言葉ですが、敬語の種類やニュアンス、そして相手に与える印象には違いがあります。
特に「〜させていただきます」は近年よく使われますが、使い方を誤ると「自己中心的な印象」を与えてしまうこともあります。一方、「開始いたします」は汎用性が高く使いやすい表現ですが、場合によっては少し簡素に聞こえることもあります。
この記事では、この二つの表現が持つ敬語としての意味や、適切に使える場面、避けるべき誤用について、イベント運営の具体的なシーンを交えてわかりやすく解説します。冒頭の挨拶で自信を持って言葉を選べるようになれば、あなたのプロフェッショナルな印象もより一層高まるでしょう。
第1章:「開始いたします」と「させていただきます」の敬語体系と機能
まず、この二つの表現の根本的な違いは、「謙譲語」と「許可の謙譲表現」という敬語の種類と、それに付随する敬意の方向性にあります。この違いを理解することが、適切な使い分けの第一歩です。
1. 「開始いたします」の機能:謙譲語と丁重さの表明
「開始いたします」は、「開始する」という動詞に、「する」の謙譲語である「いたす」を組み合わせた表現です。「いたす」は、自分の行為をへりくだらせることで、相手に敬意を示す「謙譲語II(丁重語)」に分類されます。
- 機能: 自分の行為(開始)をへりくだって丁寧に述べる。相手に敬意を示す。
- ニュアンス: 「今から会議を始めます」という事実を、丁寧に、且つ簡潔に、業務の遂行として伝える姿勢を示します。
- 適用範囲: 自分のイベント運営行為について、出席者全体に対して敬意をもって伝える、ビジネスにおける標準的かつ最も安全な表現です。
この表現は、過度な謙遜の意図を含まないため、イベント開始時の挨拶として最も汎用性が高く、どの場面でも失礼にあたることはありません。
2. 「〜させていただきます」の機能:許可と恩恵の表現の厳密性
「〜させていただきます」は、「させてもらう」の謙譲表現です。これは、単にへりくだるだけでなく、以下の二つの厳格な条件が満たされる場合にのみ、適切とされます。
- 相手の許可(許諾): その行為を行うにあたり、相手からの明示的または暗黙的な許可が必要であること。
- 自己の恩恵: その行為を行うことで、自分が何らかの利益や恩恵を得ること。
この二つの条件が、イベントの開始という当然の業務遂行に当てはまらない場合(例:許可なく当然の業務を始める場合)で安易に使うと、「許可をもらったわけでもないのに、さも恩恵を受けているかのように言う」という、自己中心的な、あるいは不自然な印象を与えかねません。これが、この表現が「過剰敬語」や「自己満足的な表現」と批判される主な理由です。
第2章:「はじめさせていただきます」の是非を問う判断の原則
会議やセミナーの開始は、主催者がスケジュールに従い、業務として行う行為です。この行為に「許可」や「恩恵」のニュアンスが本当に含まれているのかを検討することが、判断の原則となります。
1. 「はじめさせていただきます」が適切な稀有なケース
イベントの開始において、この表現が自然に使えるのは、非常に特殊で、参加者側が主催者に対して時間や場所を提供し、その許可を得てイベントを行うというニュアンスが極めて強い場面です。
- 主催者が来賓(参加者)に時間を割いてもらっているという謙虚さを最大限に示す必要がある場合。特に、参加者側がスポンサーや招待されたVIPで、主催者側が恐縮している状況。
- (例)「大変お待たせいたしました。それでは、皆様のご承諾をいただき、本日の重要なセミナーを謹んではじめさせていただきます。」(参加者が主催者側の人間より地位が高い場合など)
2. 「はじめさせていただきます」が不適切な標準的なケース(誤用注意)
通常のビジネス会議やセミナーの開始は、主催者側がスケジュールに従って当然行うべき行為であり、参加者の「許可」を得る必要は通常ありません。したがって、この表現を使うのは過剰であり、以下の点で不自然です。
- (誤用例1)「予定時刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。」解説: 会議を始めるのは主催者の役割(当然の業務)であり、許可を請う行為ではありません。不必要に冗長であり、品格を損ないます。
- (誤用例2)「これより質疑応答に移らせていただきます。」解説: 進行の一環であり、恩恵や許可は伴いません。単に「質疑応答に移ります」あるいは「質疑応答の時間とさせていただきます」で十分です。
3. 結論:イベント開始は「開始いたします」を基本とし、「いたします」で統一する
会議、セミナー、発表会など、多くのビジネスイベントの開始を告げる際は、「開始いたします」が最も無難で適切な標準表現です。この表現は、過剰な謙譲や不必要な許可のニュアンスを含まず、自分の行為を丁重に伝えるプロフェッショナルな姿勢を保つことができます。
第3章:応用編:イベント進行における「〜いたします」の徹底活用
イベントの開始だけでなく、イベント進行中にも「次へ進む」「発表する」といった様々な行為の謙譲表現を「〜いたします」で統一することが、スマートな運営につながります。
1. 次のステップへの移行と情報の提示
イベントの進行係が次のプログラムへ移行する際、すべて「〜いたします」で統一します。
| 行為 | 適切な標準表現 | NG表現(過剰な「させていただく」) |
|---|---|---|
| 休憩後の再開 | 「再開いたします」 | 「再開させていただきます」 |
| 次の議題への移行 | 「次の議題に移ります」(または「次の議題に移らせていただきます」より「次の議題に進みます」) | 「次の議題に移らせていただきます」 |
| 資料の投影 | 「資料を投影いたします」 | 「資料を投影させていただきます」 |
| 時間に関する告知 | 「休憩時間を10分とさせていただきます」 | 「休憩時間を10分とらせていただきます」 |
2. 発表・説明を始めるとき
自分が聴衆に対して発表や説明を始める瞬間も、「開始」と同様に、自分の行為をへりくだらせる「〜いたします」を使います。
- (正)「私から、企画概要について説明いたします。」
- (正)「ただ今より、本日の製品デモを実施いたします。」
ここでも「説明させていただきます」「デモを実施させていただきます」は、聴衆への配慮として過剰であり、不適切です。
3. 「お開きにする」際の表現:イベント終了の告知
イベントの終了を告げる際も、イベントの進行を締めるという自分の行為を丁重に伝えます。
- (正)「以上をもちまして、本日のセミナーをお開きといたします。」
- (NG)「以上をもちまして、セミナーを終わらせていただきます。」
第4章:言葉の重み付け:品格を高める開始前のクッション言葉
「開始いたします」をベースに、さらに丁重さや品格を高めるための、ワンランク上の表現や開始前のクッション言葉を紹介します。
1. 丁重さを加える:「まことに」や「大変」の使用
イベント参加への感謝や、待たせたことへの謝罪の言葉を添えることで、より丁重な印象を与えられます。
- (例1:定刻開始)「皆様、本日はお忙しい中、ご参加いただき、まことにありがとうございます。ただ今より、会議を開始いたします。」
- (例2:遅延時)「大変お待たせいたしました。ただ今より、開始いたします。」
2. 「始める」の丁寧語:「開会する」「開講する」
イベントの種類に応じて、より専門的で格式の高い言葉を使うことで、表現に重みが増します。
- 会議や集会: 「開会いたします」(より正式)
- 講演会やセミナー: 「開講いたします」(より正式)
3. 開始前の「お待たせしました」の敬意
開始が予定時刻より遅れた場合、「お待たせしました」を丁寧に伝えることは、開始の言葉以上に重要です。
- (正)「大変お待たせいたしました。ただ今より、開始いたします。」
ここでも、「お待たせさせていただきました」といった二重謙譲(「待つ」の謙譲と「させてもらう」の謙譲)や過剰敬語は、過剰な表現として避けるべきです。
結び:敬語は「配慮の省略」を避けるツール
「開始いたします」と「はじめさせていただきます」の使い分けは、「謙譲」と「許可/恩恵」のニュアンスの違いを理解しているかどうかの試金石です。
「はじめさせていただきます」の安易な多用は、聞き手に対して「私は許可や恩恵を受けているつもりはない」という違和感を与え、あなたの言葉から誠実さを奪います。一方、「開始いたします」は、自分の行為を控えめに、丁寧に参加者全員に伝えるという、最も基本的な配慮を表現しています。
イベントの冒頭は、参加者との信頼関係を築く最初のチャンスです。「開始いたします」という言葉の持つシンプルな丁重さを理解し、自信を持ってイベントをスタートさせてください。言葉の選び方一つで、あなたのプロフェッショナルとしての品格が決定されます。
この記事を読んでいただきありがとうございました。