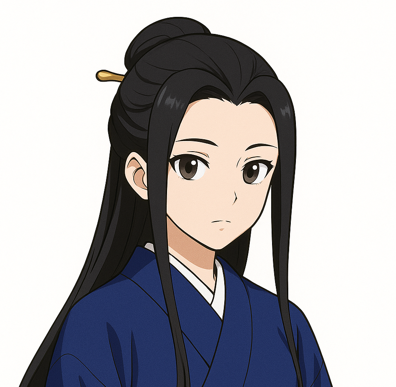ビジネスの場では、上司や顧客からの依頼や指示に対して、「わかりました」と返答する機会が日常的にあります。その際によく使われる敬語表現が「承知いたしました」と「了解しました」です。一見どちらも同じ意味に思えますが、使い方を間違えると相手に与える印象が変わってしまうことがあります。そのため、正しい理解と使い分けが大切です。
この記事では、二つの表現の意味やニュアンス、使える相手や場面、注意すべきポイントを具体的な例文やNG例とともにわかりやすく解説します。読んでいただくことで、電話やメール、社内外でのやり取りの中でも、すぐに適切な言葉を選べるようになり、あなたのビジネススキルへの信頼感もぐっと高まるでしょう。
第1章:「承知いたしました」の敬語的定義と機能
「承知いたしました」は、「承知する」という謙譲語に、さらに謙譲の補助動詞「いたす」の丁寧な過去形「いたしました」を付けた、非常に丁寧な表現です。これは、自分の動作や状態をへりくだらせることで、相手への敬意を示す構造になっています。
1. 「承知」が持つ謙譲の機能
- 意味: 相手の依頼や指示を深く理解し、謹んで引き受けたことを丁寧に伝える表現です。「知る」の謙譲語「承知する」を基本とします。
- 機能: 単に理解を示すだけでなく、相手に最大限の礼儀正しさを保ちながら、その内容を確実に実行する意志をも含む、強い信頼感を与える機能があります。
- 敬語の種類: 「承知」という言葉自体が謙譲の意味を含むため、「承知いたしました」は謙譲語に分類されます。特に、自分の動作を丁重に述べる「丁重語」としての役割が強いです。
- 適用範囲: 社外の顧客や取引先、自社の上司、目上の先輩など、敬意を示すべき相手への使用が絶対的に適切です。
2. 「承知いたしました」の最適な使用例
「承知いたしました」は、相手からの何らかの働きかけに対して、自分が行動を伴って応じる場面に最適です。
- 上司からの具体的な指示: 「本日の報告書は午後5時までに提出してください。」 → 「承知いたしました。すぐに着手いたします。」
- 顧客からの依頼: 「会議の資料を前日までに用意してください。」 → 「承知いたしました。明日午前中にはお送りいたします。」
- メールでの返答: 「ご依頼の件、確かに確認いたしました。」 → 「承知いたしました。担当者に申し伝えます。」
3. 注意点:「承知しました」との違いと二重敬語の回避
- 「承知しました」と「承知いたしました」: 「承知いたしました」は、「承知しました」よりもさらに丁寧で、強い敬意を示すため、特に格式張った場面や、極めて目上の相手には「いたしました」を使用することが推奨されます。
- 二重敬語ではない: 「承知」と「いたす」は、それぞれ異なる種類の謙譲語の要素を含みますが、文法上は「承知する」という動詞に謙譲の補助動詞「いたす」を付けており、二重敬語にはあたりません。安心して使用できます。
第2章:「了解しました」の敬語的限界と適切な適用範囲
一方、「了解しました」は「了解する」に丁寧語「しました」を付けた表現です。この表現の敬語としての位置づけは、「承知いたしました」とは大きく異なります。
1. 「了解」が持つニュアンスとカジュアルな機能
- 意味: 物事の意味・内容・事情などを理解したこと、または理解した上で承認したことを伝える言葉です。
- 機能: 丁寧語であるため、形式的には敬語ですが、その語彙自体に「相手の事情を認める」というニュアンスが含まれることから、目上の相手に対しては不適切とされる場合があります。カジュアルでスムーズなやり取りに向きます。
- 敬語の種類: 丁寧語に分類されます。謙譲の意図は含まれません。
- 適用範囲: 社内の同僚や部下、親しい間柄の先輩、チーム内のカジュアルな連絡に適します。
2. 「了解しました」の最適な使用例
「了解しました」は、社内での情報共有や、確認事項に対する返答など、簡潔さが求められる場面で有効です。
- 同僚への連絡: 「明日の資料、コピーして会議室に置いておいてください。」 → 「了解しました。」
- チーム内チャット: 「プロジェクト進捗の共有、承知しました。」 → 「了解です。(または、了解しました)」
- 社内での部下への返答: 「田中さん、その件で問題ないよ。了解しました。」
3. 注意点:「了解いたしました」は避けるべき
「了解いたしました」という表現は、「了解」に謙譲語の「いたしました」を付けているため、一見丁寧に見えますが、多くの敬語の専門家やビジネスマナーにおいて、不適切または不自然であるとされています。これは、「了解」という言葉自体が謙譲の意図を持たないため、謙譲語の「いたしました」と組み合わせても、目上の相手に対する敬意を十分に伝えられないためです。
- 目上の相手や社外には、必ず「承知いたしました」か「かしこまりました」を使用すべきです。
第3章:即答でわかる!「敬意の方向」と「内容の重さ」による使い分け
「承知いたしました」と「了解しました」をすぐに使い分けるコツは、「敬意の方向」と「内容の重要度」を意識することです。
1. 敬意の方向の鉄則
話す相手が敬意を示すべき対象の場合は、自分の行為を控えめに伝える「謙譲語」を選ぶのが基本です。
| 相手 | 適切な表現 | 敬語の種類 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 目上・社外 | 承知いたしました | 謙譲語 | 自分の「わかった」行為を控えめに伝え、相手を立てる表現です。 |
| 同僚・目下 | 了解しました | 丁寧語 | 対等な立場で、簡潔かつ丁寧に伝えられます。 |
2. 内容の重さ(シーン)による使い分け
- 重要な依頼や公式な場:相手への敬意を強く示すため、「承知いたしました」を選びます。
- 日常的な情報共有やカジュアルな場:スムーズさを優先し、「了解しました」を使います。
3. 最上級の敬意:「かしこまりました」の活用
さらに丁寧に、謹んで承諾するニュアンスを伝えたい場合は、「かしこまりました」が便利です。接客や電話応対の初期対応で特に役立ちます。
- 使用例:「ご注文、確かに承りました。」 → 「かしこまりました。すぐに手配いたします。」
第4章:状況別・媒体別の具体的な使い分け
1. 電話応対での使い分け
電話は声や言葉遣いが印象を左右するため、原則として丁寧な表現を選びます。
- 顧客・取引先:「承知いたしました」「かしこまりました」
- 社内上司:「承知いたしました」(必要に応じて「かしこまりました」)
- 社内同僚:「了解しました」
2. ビジネスメールでの使い分け
- 上司からの指示:「承知いたしました。〇〇までに完了させます。」
- 顧客への返信:「ご依頼の件、承知いたしました。改めてご連絡差し上げます。」
- NG例:メールの結びで「了解です」は、カジュアルすぎるため避けましょう。
3. チャット・ウェブ会議での使い分け
- 上司・目上:「承知いたしました」を略した「承知しました」程度で十分
- 同僚・チーム内:「了解しました」「了解」で問題ありません
第5章:まとめとプロフェッショナルな対応の極意
「承知いたしました」と「了解しました」の使い分けを身につけることは、ビジネスマナーの基本であり、相手への敬意や配慮を伝えるための大切なスキルです。
1. 最終確認:機能の違い
- 承知いたしました:謙譲語で、理解と行動への意思を含む。社外や上司向けに最適。
- 了解しました:丁寧語で、単に理解したことを伝える。同僚や部下向け。
2. プロフェッショナルな対応のコツ:行動の補足
「承知いたしました」だけでは理解を伝えるだけに留まる場合があります。信頼感を高めるためには、行動を約束する一言を添えると効果的です。
- 「承知いたしました。すぐに対応いたします。」
- 「承知いたしました。〇〇までにご報告いたします。」
- 「承知いたしました。担当者に申し伝えます。」
状況や相手に合わせて適切な「承知いたしました」を選び、必要に応じて「すぐに対応します」や「担当者に伝えます」といった具体的な行動を添えることで、自然で信頼感のある返答ができます。この違いを意識するだけで、ビジネスでのコミュニケーションの印象がぐっと良くなり、周りからの評価も高まるでしょう。
この記事を読んでいただきありがとうございました。