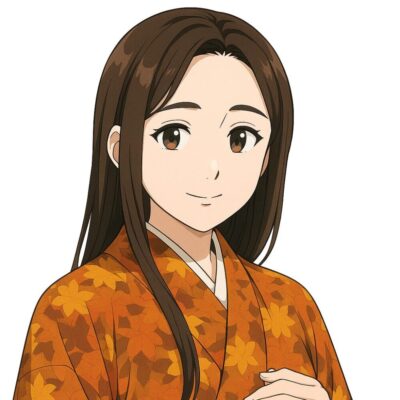ビジネスシーンで、相手の知識や情報を尋ねたり、自分がその事柄を知っていることを伝えたりする際、「知っていますか?」「知っています」といった直接的な表現では、稚拙で失礼な印象を与えてしまいます。そこで重要となるのが、「知る」という動作の敬語表現です。
「存じます」「ご存知ですか」といった言葉は日常的に使われますが、この二つは、主語が「誰であるか」によって、適切な使い方が全く異なります。この使い分けを誤ると、相手への敬意が逆転する「尊敬語の誤用」につながり、信用を損ないかねません。
本記事では、「存じます」「ご存知ですか」が持つそれぞれの意味と、敬語の基本である「主語」に基づいた明確な使い分けを徹底解説します。さらに、さらに丁寧な謙譲語「存じ上げる」や、質問メールで使える適切なクッション言葉といった応用マナーまでご紹介します。この記事を読めば、あなたは自信を持って、知識に関するコミュニケーションができるようになるでしょう。
1. 「存じます(存じる)」の正しい使い方と「謙譲語」の役割
「存じる(ぞんじる)」は、「知る」の謙譲語です。「存じます」はその丁寧語形であり、自分の行為をへりくだって表現することで、相手に敬意を示す役割があります。
1-1. 「存じます」が適している主語と例文
「存じます」は、話の主語が「自分」や「自社の人間」である場合にのみ使用します。相手の知識や状態を指す際には絶対に使用してはいけません。
- 適している主語:自分、自社の社員。
- (例文1:知識の有無)「ご質問の件、確かに存じております。」(=知っています)
- (例文2:意見・考え)「私としては、その点は問題ないと存じます。」(=考えます/思います)
- (例文3:自分の気持ち)「ご多忙の折、恐縮に存じます。」(=思います)
「存じる」は、「知る」の謙譲語であると同時に、「思う」「考える」といった思考の謙譲語としても非常に幅広く使われます。
注意点: 自分の動作に対して尊敬語を重ねる「存じさせていただきます」という表現は、過剰な謙譲語として避けるべきです。シンプルに「存じております」で十分です。
1-2. 「存じ上げる」:人や物事への最上級の謙譲語
「存じ上げる(ぞんじあげる)」は、「知る」の謙譲語である「存じる」に、さらに謙譲の補助動詞「あげる」を加えた最上級の謙譲語です。主に、人や、尊敬するに値する物事に対して使われます。
- (例文)「〇〇社長のお名前は、以前より存じ上げております。」
情報や事柄に対しては「存じる」、人やその人の功績に対しては「存じ上げる」と使い分けることで、より深い敬意を示すことができます。
2. 「ご存知ですか」の正しい使い方と「尊敬語」の役割
「ご存知(ごぞんじ)」は、「知る」の尊敬語です。これに「〜ですか」といった丁寧な言い方を付け加え、相手の知識の状態を尋ねる際に使われます。
2-1. 「ご存知ですか」が適している主語と例文
「ご存知ですか」は、話の主語が「相手」や「第三者の目上の方」である場合にのみ使用します。自分の知識や状態を指す際には絶対に使用してはいけません。
-
適している主語:上司、目上の方、取引先、顧客など。
-
(例文1:相手への質問)「弊社の新製品について、ご存知でいらっしゃいますか。」
-
(例文2:間接的な質問)「〇〇様のほうは、その件をご存知でしょうか。」
-
(例文3:説明時)「皆様ご存知の通り、このプロジェクトは非常に重要です。」
注意点: 「ご存知」自体が尊敬語であるため、「ご存知になられましたか」といった二重敬語は誤用とされます。また、「ご存知です」は丁寧語として使われますが、目上の人には「ご存知でいらっしゃいますか」や「ご存知でしょうか」といった形を使う方がより丁寧です。 3. 【実践】「存じる」と「ご存知」の使い分けチェック 敬語の使い分けの原則は、「誰の動作・状態か」という主語の確認です。これを明確にすれば、間違いを防げます。 3-1. 敬語の「主語」判定Q&A
| 伝えたい内容 | 主語 | 適切な敬語 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 相手の知識の有無を尋ねる | 相手 | ご存知ですか / ご存知でしょうか | 相手の状態を尊敬語で尋ねる |
| 自分の知識の有無を伝える | 自分 | 存じております | 自分の状態を謙譲語で伝える |
| 自分の考えを述べる | 自分 | 存じます / 存じ上げております | 「思う/考える」の謙譲語として使用 |
| 取引先が自社の田中を知っているか尋ねる | 取引先(相手) | ご存知でしょうか | 相手の状態を尊敬語で尋ねる |
3-2. 敬語が逆転するNGパターン
「知る」の敬語表現で最も多い誤用は、自分の状態に尊敬語を使ってしまうパターンです。
- NG例1:「お客様、弊社の〇〇部長をご存知でいらっしゃいますか。」(身内を立てる尊敬語を使用)
- OK例1:「お客様、弊社の〇〇部長はご存知でしょうか。」
- NG例2:「私どものほうは、その件はご存知ありません。」(自分の状態に尊敬語の打ち消しを使用)
- OK例2:「私どものほうは、その件は存じておりません。」
- NG例3:「部長がその件を存じておりませんでした。」(相手の状態に謙譲語を使用)
- OK例3:「部長がその件をご存知ありませんでした。」
4. 質問メールで差がつく敬語マナーと応用表現
「知る」の敬語以外にも、知識に関する質問や報告には、丁寧さを高める応用表現があります。
4-1. 「知らない」を伝える際の丁寧表現
「存じておりません」は丁寧ですが、さらに「恐縮」や「申し訳ない」という気持ちを付け加えることで、相手への敬意を示せます。
- 「申し訳ございません、現在のところ、その件につきましては存じておりませんでした。」
- 「恐縮ながら、詳細については把握しておりません。」(「知る」よりも「掴んでいる」というニュアンス)
4-2. 相手の知識を仮定する際のクッション言葉
相手に質問する際、「知っているはず」という前提で尋ねるのは失礼にあたります。相手の知識を尊重するクッション言葉を使いましょう。
- 「もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。」
- 「ご存知のことと存じますが、念のためご確認させていただきます。」
まとめ
本記事では、「存じる」と「ご存知」を軸に、「知る」という行為の敬語表現を解説しました。
「知る」の敬語の使い分けは、以下のルールで必ず守りましょう。
- 主語が相手(目上)の場合: 尊敬語の「ご存知」を使う。(例:ご存知ですか)
- 主語が自分(または自社)の場合: 謙譲語の「存じる」「存じ上げる」を使う。(例:存じております)
このルールを徹底し、相手への敬意を適切に伝えることで、あなたのビジネスパーソンとしての信頼性は格段に向上するでしょう。ぜひ、この記事を参考に敬語を使いこなしてください。
この記事を読んでいただきありがとうございました。